
こちらのページでは、名古屋大学の入試を突破した現役の学生により、入試科目と試験時間・配点、各科目の傾向と対策が記載されています。
名古屋大学の入試を受けることを考えている高校生の方々は、現役学生による信憑性の高い情報を活かし、今後の受験勉強に役立てましょう。
名古屋大学の科目別入試傾向と対策
現役の名古屋大学の学生の経験から、各科目の入試傾向と対策をお伝えします。高い信憑性に基づく情報をご覧ください。
執筆者:名古屋大学教育学部の現役学生家庭教師のK.K先生
国語の傾向と対策

問題構成
大問3個で構成されており、大問1は現代文、大問2は古文、大問3は漢文となっています。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
大問1は、標準的な現代文の読解問題です。漢字は毎年読み書き合わせて10問出題されます。
要約問題は出題されず、文章中の意図の説明や、理由説明を求める設問が多く見られます。字数は他の大学に比べて少なく、多くても200字以内になっています。内容一致を選ぶ記号問題も頻出です。
大問2は古文で、名古屋大学は和歌がほとんど毎年出題されます。冒頭に3問ほど漢字の読みがあり、その後は現代語訳や説明問題が中心となります。他大学と比べて記述量が多いため対策は必須です。年によっては、修辞が問われる場合もあります。また、ここ2年ほど最後に文学史の記号問題がで出題されています。
大問3は漢文で、はじめに3問ほど漢字の読みが出され、その後は傍線部の説明など細かい記述問題が続きます。また、名古屋大学の特徴として、最後に文章の趣旨を200字以内でまとめる問題が最後に出題されます。ここ10年をみても例外はないため、ほぼ必ず出ると考えてよいでしょう。
全体的な対策のポイント・注意点
基本ではありますが、問題文をよく読むようにしましょう。例えば、漢字の読みはカタカナで書かなければいけなかったり、古文の説明問題で、「どのような心情を踏まえて訳しなさい」といった条件が問題文に書かれていたりすることがあります。こうした指示は見落としやすいので、何を聞かれているのかをしっかりと把握してから答えるようにしましょう。
各問題の対策のポイント・注意点
漢字の読みはカタカナで書かなければいけないので間違えないよう注意が必要です。漢字程度と思いがちですが、10問も出るので確実に得点することが大切です。
古文は和歌についての勉強を必ずしておきましょう。特に、修辞法を理解しておくと直接的に使える場合は少なくても、スムーズに訳せるようになるので必ず役に立ちます。また、漢文については要約問題があるので、各問題だけでなく全体の流れを把握しておくことが大切です。
数学(文系)の傾向と対策
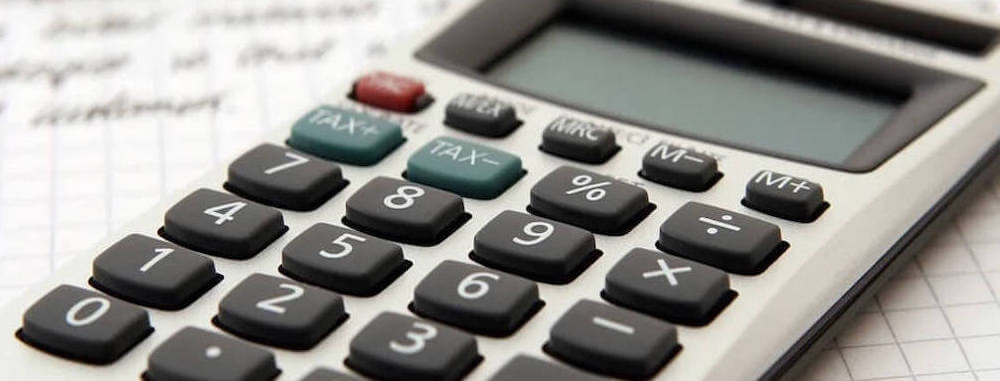
問題構成
大問3つから構成されており、それぞれに小問がある場合もあれば全くない場合もあります。ただし、小門の有無に関わらず部分点が与えられます。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
試験時間は90分なので大問1つあたり30分かけることができます。
出題傾向は年によって様々ですが、ほぼ毎年確率に関する問題が出題されます。文系数学では基本的な確率の問題が中心ですが、年によっては理系向けでよく出題される確率漸化式が出る場合も多いです。文系でも理系とほぼ同じレベルの問題がでる場合が多いので難易度はやや高めと言えるでしょう。
その他は図形と二次関数の複合問題や、整数の問題などが頻出です。ベクトルは過去10年で1度しか出題されておらず、出題される可能性はかなり低いと言えます。
全体的な対策のポイント・注意点
まずはしっかり過去問に取り組みましょう。10年分ほど解くと、出やすい分野を網羅することができるうえ、問題の雰囲気や時間配分もつかむことができます。
各問題の対策のポイント・注意点
確率は問題設定が複雑なものが多く見られますが、しっかりと文章を読み解けば比較的スムーズに解ける問題が少なくありません。頻出なのでしっかりと対策をしておくことが大切です。また、確率漸化式については、慣れも必要なので、過去問や類似問題を解き、感覚を掴んでおきましょう。
微積の問題については過去問を10年分ほど網羅することで必要な解き方は一通り学ぶことができます。整数の問題は証明問題が出題されることが多いので、過去問や問題集の解法をしっかりと理解しておくことが大切です。
名大数学は基礎力だけでは解くことが難しい問題も多いですが、2次試験の問題を数多くこなすことで徐々に記述力が身についていきます。とにかく問題にたくさん触れましょう。
執筆者:名古屋大学工学部の現役学生家庭教師のT.K先生
数学(理系)の傾向と対策
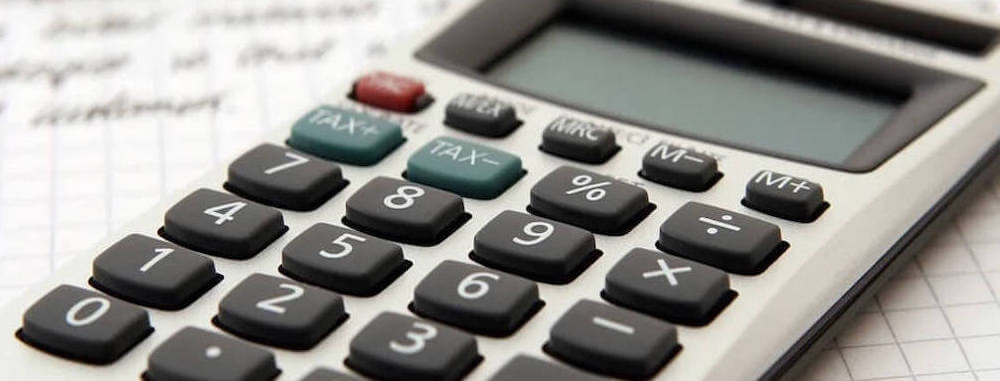
問題構成
名古屋大学の数学は、大問4個を150分で構成されており、じっくり時間をかけて解くことができます。また、各大問ごとに小問が2〜4問出題されます。すべての問いに対して記述が求められ、高い論証力が必要です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
試験の難易度は、標準問題から難問までがバランスよく出題されています。
各大問、(1)(2)は基本的な問題が多く、(3)は難問となる傾向にあります。頻出分野は微積分、確率、複素数平面、ベクトル、整数が挙げられます。特に、整数や複雑な式の論証問題は難易度が高くなることが多いです。論証を組み立てる際には、小問間のつながりを見抜いて、式変形を工夫する力が求められます。
また、微積分や確率の分野では、計算量の多い問題が出題されます。この2分野は、(1)(2)の問題をそのまま利用して、残りの問題を解くことが多いため、(1)(2)から丁寧に解いていきましょう。
全体的な対策のポイント・注意点
各大問の(1)(2)を確実に得点できるように、青チャートやFocus Goldを繰り返し解いて基本を完璧にしましょう。また、大問を2つほど完答できるとぐっと合格に近づきます。完答できそうな問題を見極めて解くことがポイントです。
計算量が多いですが、試験時間は比較的長いため、焦らず正確に解くことを意識するとよいでしょう。昨年は大幅に易化したので、今年は難化が予想されますが、取れる問題を確実に解答することが大切です。
各問題の対策のポイント・注意点
微積分、複素数は(1)(2)は解きやすいことが多いので、青チャートなどで典型問題を完璧にしておきましょう。
確率は多くの問題に触れて、思考パターンを身につけておくことが大切です。特に、確率漸化式に慣れておくとよいでしょう。筆者は、青チャートやスタンダード数学演習で対策しました。
難易度の高い論証問題は、過去問を中心に対策をしましょう。平均値の定理などを利用した証明問題に慣れておくことも必要です。また、自分の解答に、論理の飛躍はないか、十分な記述がされているかを添削してもらうことも大切なポイントです。
この分野に限らず、数学は必ず添削をしてもらいその結果をもとに、復習を重ねる学習方法をおすすめします。
執筆者:名古屋大学文学部の現役学生家庭教師のO.M先生
地理の傾向と対策

問題構成
大問は3題(文学部などでは4題の年もある)で、試験時間は90分です。
記述問題と論述問題が出題されます。記述問題は比較的オーソドックスで、基礎知識がしっかり身についていれば解答できる問題となっています。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
大問はそれぞれテーマによって分かれています。
大問1は自然地理分野(気候・地形・航路図示など)が主に出題されます。基本的には教科書〜赤本レベルの知識で解くことができる難易度です。資料から情報を読み取り、説明する形式で、記述力と知識理解力が求められます。
大問2は社会地理分野(農業区分、産業構造、社会環境など)が主に出題されます。地図塗り・統計グラフの読み取りを伴う実践重視の設問が多いことが特徴です。ここでは基本知識に加えデータ把握や論理的説明力も求められます。
大問3は地誌(特定地域)や都市・環境問題など、幅広いテーマから出題されます。昨今は都市環境や一次資料に基づく出題が増加傾向にあります。分析・考察型の論述がメインとなっており、背景を踏まえた説明が求められます。
文学部などでは大問4題構成で、地誌や論述重視の問題が出題されることも あります。
全体的な難易度については、「基礎〜標準」レベルであり、知識だけでなく考察的論述が必要になっています。
全体的な対策のポイント・注意点
統計・地図・図表の読み取りと、それを根拠に論理的に記述する力が求められます。単なる知識の暗記ではなく、因果関係や背景を意識して説明できるようにすることが重要です。
各問題の対策のポイント・注意点
大問1では地形図や地形の成因、気候との関連などがよく問われるため、地形図の読解演習や、地形・気候のメカニズムの理解を深めておくとよいです。
大問2ではグラフや表を正確に読み取り、地域差の背景を論理的に説明する力が必要です。「なぜそうなるのか」「ほかの地域と比べてどうか」を自分で説明する力をつけたり、用語だけでなく「プロセス」や「因果関係」を意識することが必要です。問題集や過去問を解く際にもその点を意識しながら取り組むと良いでしょう。
大問3は総合的・応用的な記述問題が出題されるため、複数の要素を組み合わせて論述する力が必要です。開発・環境・SDGsなど現代的なテーマも多いため、時事的事柄に日ごろから興味関心を持ち、知識を身につけるだけでなく、その知識と地理的視点を結びつける練習が有効と言えるでしょう。
執筆者:名古屋大学文学部の現役学生家庭教師のR.T先生
世界史の傾向と対策

問題構成
例年穴埋めや語句、短文記述を中心とした3題と論述1題を含む4題構成になっています。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
例年出題される論述問題は、年によって変動があるものの、5つ程度の語句が提示され5、それらを全て用いて約400字の指定された字数内で論述する形式になっています。
その他の大問では、文章や資料を踏まえ、それに関する語句や短文の記述問題が出題されます。
短文記述では貿易の特徴、各王朝の政治方針や施行した制度の説明を求める問題が頻出です。また、特定の出来事に至るまでの経緯を説明させる設問もよく見られます。
語句記述では文章内に書かれている語句に関連したことを問われます。特によく出題されているのは宗教に関する問題です。なお昨年は出題されませんでしたが、一昨年以前には資料が5つほど提示され、それに関する記述問題とあわせて、提示された資料を年代順に並び替え、指定された順番のものを解答させる形式の問題も出題されていました。
全体的な対策のポイント・注意点
まずは教科書の内容を正確に、徹底的に覚えることが重要です。
名大の二次試験は難問は少なく、基本的な歴史の流れをしっかりと把握できていれば取り組みやすい問題が多く出題されます。特に語句記述は知識があれば確実に得点することができます。縦の繋がりを掴むことはもちろん、名大の世界史では横のつながりが問われることも多いため、しっかりと理解しておきましょう。
教科書では地域ごとの歴史が点々と登場するため、地域ごとに分けられている参考書を手に入れると勉強がしやすくなります。
各問題の対策のポイント・注意点
論述問題では地域、時代が幅広く出題されます。ここでも政治制度や税制などはよく出題されますので押さえておくと安心です。
また、シンプルな語句説明と時代の流れを記述する問題も出題されるため知識が特定の分野に偏らないようにバランスよく学習すると良いでしょう。
穴埋めや語句の記述は一問一答の問題集を繰り返し解き、正しい知識をつけることで対応できます。問題文中には難しい用語が含まれる場合もありますが、問題文をしっかり読み、出来事と出来事の繋がりを把握すれば十分に解くことができます。
執筆者:名古屋大学医学部の現役学生家庭教師のN.M先生
物理の傾向と対策
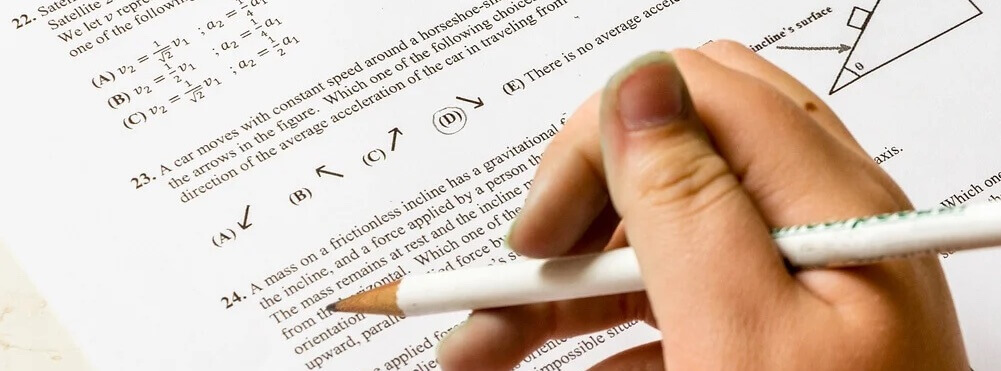
問題構成
名古屋大学の物理は、大問3題で構成され、力学・電磁気・熱力学・波動などの分野から幅広く出題されます。特に、力学は毎年必ず出題される傾向にあります。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
答えのみを記入する問題の他に記述式の問題も出題されるため、答えだけではなく導出過程や物理的な意味を説明できる力が求められます。典型的な公式の当てはめだけでは解けない問題も多く、グラフの読解や、複数の現象の統合的な理解が問われます。
また、問題文が長く、与えられる情報を整理しながら思考する力が必要です。難易度には、年度によってばらつきがある印象です。突然難化または易化することもあります。名古屋大学の過去問を複数年分解いておくことで、難易度の変化にも対応できるようにしましょう。
全体的な対策のポイント・注意点
力学や電磁気の問題はほぼ毎年出題されているため、重点的に対策すると良いでしょう。問題文が長いため、本文中の条件や情報を読み取りながら拾っていく練習を、過去問演習等を通じて解養っておくことが大切です。
各問題の対策のポイント・注意点
特に多く出題される力学と電磁気については、力学では、エネルギー保存則や運動方程式を、電磁気では回路や電場・磁場の関係を深く理解しておくことが重要です。
名古屋大学では実験を想定した問題やグラフの選択問題なども出題されることもあるため、教科書の章末問題やセンター試験・共通テスト過去問も活用しましょう。教科書のグラフなどを見ておくと役立つ可能性があります。
記述式の問題については、論述が必要な問題に慣れておくことで高得点が狙いやすくなります。
化学の傾向と対策

問題構成
名古屋大学の化学は大問5題構成で、理論化学・無機化学・有機化学の3分野からバランスよく出題される傾向があります。近年は理論化学と無機化学で3題、有機・高分子で1題ずつ出題される形式が続いています。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
計算問題と考察問題が混在しており、思考力と論述力が問われます。反応の仕組みや化学平衡、電池や熱化学、官能基の推定や構造決定など、典型問題の応用にあたる問題が多く出題されます。また、化学の知識を組み合わせて考察する問題も出題されることがあります。
問題の難易度は標準~やや難で、教科書や基礎問題集の内容をしっかりと理解していることが前提となり、応用力も必要です。教科書の内容を大きく超えるような問題は見られないものの、知識の暗記だけでは対応が難しく、論理的に説明できる力が求められます。
全体的な対策のポイント・注意点
名古屋大学の化学は暗記と計算の融合型の出題が特徴です。基礎の徹底と応用練習をバランスよく行いましょう。また、年度によっては分量が多くなることもあるため、時間を意識して過去問を解くことも必要です。理科2科目で計150分の試験形式のため、通しで解く練習をしておくとよいでしょう。
各問題の対策のポイント・注意点
理論化学では、計算力と理論的な読解が不可欠です。特に気体・溶液・平衡・酸塩基・電池などの分野は毎年のように出題されており、公式の暗記だけではなく、なぜそのようになるのかを説明できる力をつけておくことが必要です。
無機化学や有機化学では、反応のパターンや色・沈殿・生成物などを整理し、視覚的に覚えておくと良いでしょう。特に有機化学の構造決定問題は文章量も多く、論理的思考が求められるため、過去問で慣れておく必要があります。
執筆者:名古屋大学農学部の現役学生家庭教師のK.K先生
生物の傾向と対策

問題構成
近年は問題Ⅰ〜問題Ⅳの4問構成です。2025年度入試は3問構成へ変化しました。1つの大問につき、導入文が2〜4個あり、それぞれの文に対して小問が複数出題されます。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
名大生物は大問1つとっても、複数の分野にまたがる融合問題が出題されることがほとんどで、出題分野も分子生物学から生態系など、ミクロな視点からマクロな視点までさまざまです。中でも、遺伝に関する分野は頻出です。
例年、各大問には導入文が付されており、そのトピックに関する語句補充問題が数題出題されます。解答すべき語句は基本的なものであることが多いです。また、他大学と比べても、導入文が非常に長いことが名大生物の特徴です。特に、大問後半の考察問題は難易度が高く、前半部分の導入文にヒントが隠されていることもしばしばです。そのため、一つ一つ内容を理解して解き進めていくことが重要です。
全体的な対策のポイント・注意点
名大生物受験生は、まず導入文や実験説明文の文量に慣れ、読解力を高める必要があります。実験説明文には必ず「この実験の目的は何か」が書かれているはずです。大問を通して実験の目的を見失わず、試験区の条件をきちんと押さえていくことが読解の鍵であり、考察問題を有利に解き進めることにつながります。
また、名大生物の答案用紙には罫線がありません。とはいえ、解答欄のサイズにはそれぞれ適切な文量というものがあります。名大専用の対策問題集には解答欄のサイズが各問題に付されているはずです。適切な量感を掴むためにも、実際に解答欄を自分で作って、過去問演習をすることを強くおすすめします。
各問題の対策のポイント・注意点
語句補充問題は基本的な問題が多く出題されます。また、語句の定義説明なども時々出題されます。ここでの失点は痛手ですから、過去問演習で間違えた時はその分野を教科書や資料集を使って十分補強しましょう。前述の通り、考察問題はそれ以前の問題と関連していることが多いですが、中には途中で理解につまずいても得点できる問題はあります。問題と最後まで向き合い、少しでも得点の可能性がある問題に手をつけていきましょう。
名大生物は時間に余裕がありません。基本的な問題を手早く解き、考察問題に余力を残すためにも、時間があるうちは名大にこだわらず、色々なバリエーションの問題を使って演習を積むことも、解くスピードを上げる良い対策になるはずです。
執筆者:名古屋大学法学部の現役学生家庭教師のY.S先生
英語の傾向と対策

問題構成
長文読解2問、会話文読解1問、英作文1問
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
近年の長文読解では記号問題が非常に多く出題されます。
出題形式は、空所補充や内容一致、同義語選択等、多岐に渡ります。和訳問題や説明問題も近年減少しつつありますが、大問につき2問ほど出題されています。
難易度は、長文どちらか1題は抽象度や語彙のレベルが高い一方、もう1題は取りかかりやすい文章である傾向があります。英検準1級レベルの語彙力を有していれば長文読解で困ることはないでしょう。
会話文読解は英語では最も難易度が低い大問で、あるテーマに関する2人の会話の形式で出題されることが多いです。名大受験生レベルであれば難しくはない記号問題が大半を占めますが、大問の最後にテーマに関する20語〜50語程度の英作文が出題されます。ここでは難易度の高い問いが出題されることもあるため要注意です。
名大の英作文問題は出題パターンが定まっていません。あるデータに関する表やグラフの問題、錯覚に関する問題、意見を問う問題などと幅広く出題されています。
河合塾の名大オープンでは長文問題が約120点、会話文問題が約40点、英作文問題が約40点という予想配点となっています。
全体的な対策のポイント・注意点
名大の英語は英作文の比重が極めて小さいです。英作文の対策は共通テスト後に開始しても十分間に合うでしょう。不安がある場合は秋頃から始めるのも一つの手です。
一方、文章読解の配点はかなり大きいため、十分な対策が必要です。高2までに共通テストレベルの語彙力と読解力を身につけ、高3では英文解釈や長文読解の演習を積みながら、名古屋大学レベルの語彙力を確立していくという学習ペースが望ましいでしょう。
各問題の対策のポイント・注意点
長文読解は名大英語を突破できるかできないかの大きな分かれ目です。難しい方の長文を6割程度、易しめの方を7割程度取れば合格点に乗ることは可能でしょう。英語を得点源にしたい受験生は前者は7割、後者は8割得点することが理想です。
名大の長文問題は記号問題が多く、慣れが必要です。ある程度力がついてきたら私立大学の英語問題を利用してマークの演習も積みましょう。説明問題や和訳問題も参考書で徹底的に対策し、名大や他の旧帝大の記述問題も解きましょう。
会話文問題に特別な対策は必要ありません。直近5年の過去問を繰り返す解くことで問題に慣れ、スピード感を養いましょう。本番ではこの大問をいかに早く終わらせられるかが重要となります。
英作文対策は他大学の英作対策と大差ありません。和文英訳と英作文を参考書等で強化した後、過去問を解きましょう。解いた後、自分の中で完結させてはいけません。必ず添削を受け、書き直しをすることが大切です。
オンライン家庭教師で
名古屋大学に合格!
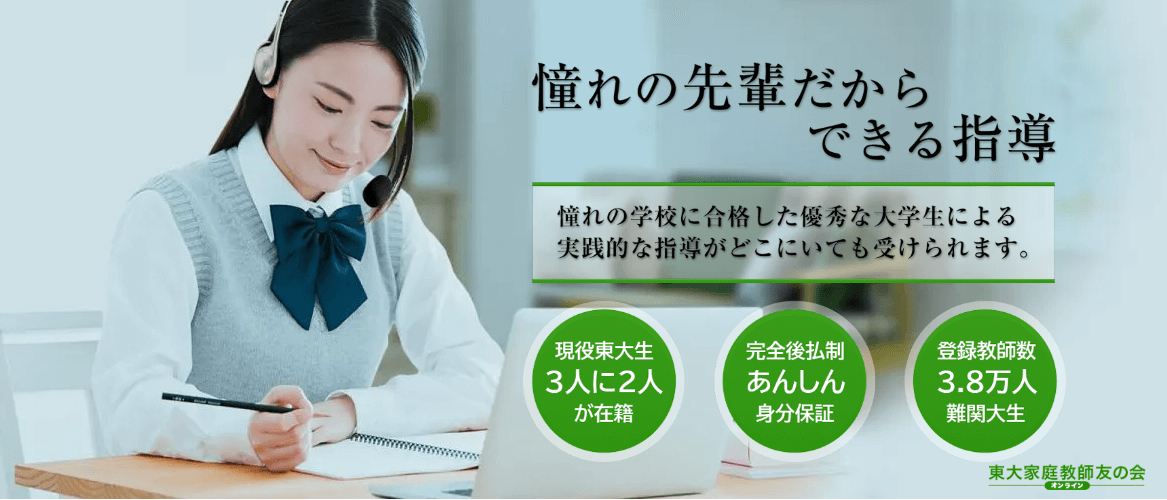
オンライン東大家庭教師友の会は、3.8万人の難関大生家庭教師が在籍する、オンライン家庭教師サービスです。
オンライン指導のため、北海道〜沖縄まで全国どこからでも難関大生による質の高い指導を受けることができます。
無料の資料請求や無料の体験授業を実施しておりますので、ぜひお試しください。
名古屋大学の学部/学科別の入試科目・配点
以下、入試科目・配点等の情報は全て「2025年度入試要綱」より抜粋しています。最新の入試情報は、名古屋大学HP等でご確認ください。
文学部
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から2科目・・・200点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物基・化基・生基・地学基)から2科目・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1200点
国語(国語総合、現代文B、古典B)・・・400点
地歴(世B・日B・地理B)から1科目・・・200点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)・・・200点
外国語(英語)・・・400点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
教育学部
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1又は2科目・・・100点又は200点
理科(物基・化基・生基・地学基・物理・化学・生物・地学)から1又は2科目・・・100点又は200点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
※地歴公民理科の中から3科目。ただし。基礎を付した科目は2科目で1とする。
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
個別学力検査・配点合計1800点
国語(国語総合、現代文B、古典B)・・・600点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)・・・600点
外国語(英語)・・・600点
法学部
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から2科目・・・200点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物基・化基・生基・地学基)から1科目・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計600点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)・・・200点
外国語(英語)・・・200点
その他(小論文)・・・200点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
※小論文は高等学校の地歴,公民の学習を前提とする。
経済学部
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から2科目・・・200点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物基・化基・生基・地学基)から1科目・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1800点
国語(国語総合、現代文B、古典B)・・・500点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)・・・500点
外国語(英語)・・・500点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
情報学部自然情報学科
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1科目・・・100点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物理・化学・生物・地学)から2科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1100点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)・・・400点
理科(物基/物理・化基/化学・生基/生物・地学基/地学)から1科目・・・300点
外国語(英語)・・・400点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
情報学部人間・社会情報学科
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から2科目・・・200点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物基・化基・生基・地学基)から2科目・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1100点
地歴公民・数学(世B・日B・地理B・倫・政経)(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B)から1科目・・・400点
外国語(英語)・・・700点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
情報学部コンピュータ科学科
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1科目・・・100点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物)と(化・生・地学)から1科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1300点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)・・・500点
理科(物基/物理・化基/化学・生基/生物・地学基/地学)から2科目(ただし物基/物理を含むこと)・・・500点
外国語(英語)・・・300点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
理学部
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1科目・・・100点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物理・化学・生物・地学)から2科目(ただしに物理・化学いずれかを含むこと)・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1450点
国語(国語総合、現代文B)古文・漢文を除く・・・150点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)・・・500点
理科(物基/物理・化基/化学・生基/生物・地学基/地学)から2科目(ただし物基/物理、化基/化学のいずれかを含むこと)・・・500点
外国語(英語)・・・300点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
医学部医学科
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1科目・・・100点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物理・化学・生物)から2科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1650点
国語(国語総合、現代文B)古文・漢文を除く・・・150点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)・・・500点
理科(物基/物理・化基/化学・生基/生物)から2科目・・・500点
外国語(英語)・・・500点
その他(面接)英文の課題に基づいた面接
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
医学部保健学科
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1科目・・・100点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物理・化学・生物)から2科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1650点
国語(国語総合、現代文B)古文・漢文を除く・・・150点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)・・・500点
理科(物基/物理・化基/化学・生基/生物)から2科目・・・500点
外国語(英語)・・・500点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
工学部
共通テスト・配点合計600点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1科目・・・100点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・100点
理科(物理・化学)・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・100点
個別学力検査・配点合計1300点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)・・・500点
理科(物基/物理・化基/化学)・・・500点
外国語(英語)・・・300点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
農学部
共通テスト・配点合計900点
国語(国語)・・・200点
地歴公民(世B・日B・地理B・倫・政経)から1科目・・・100点
数学(数学Ⅰ・数学A)と(数学Ⅱ・数学B・簿・情報)から1科目・・・200点
理科(物理・化学・生物・地学)から2科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
個別学力検査・配点合計1550点
国語(国語総合、現代文B)古文・漢文を除く・・・150点
数学(数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B)・・・400点
理科(物基/物理・化基/化学・生基/生物)から2科目・・・600点
外国語(英語)・・・400点
※英語は「コミュニケーション英語Ⅰ」・「コミュニケーション英語Ⅱ」・「コミュニケーション英語Ⅲ」・「英語表現Ⅰ」・「英語表現Ⅱ」の5科目をあわせて出題。
オンライン東大家庭教師友の会が選ばれる3つの理由
ハイレベルな教師陣!
当会に在籍する家庭教師は全て難関大生または難関大卒であり、彼らは受験事情に精通し独自の勉強法やノウハウを持っています。また、採用率20%の厳しい選考を行い、教師としての指導力・優れた人間性・指導の戦略性を持った人材のみを採用しています。オンライン東大家庭教師友の会の教師の質は国内トップクラスです。
相性のいい教師が見つかる!
当会には38,000名の現役難関大生やプロの講師が在籍しています。教師数が多いということはそれだけ多くの教師を選べるということです。学習状況や希望する教師条件のヒアリングと、厳格で緻密な選考を通して、お子様にぴったりな教師をご紹介します。生徒の「勉強をしたい」という気持ちを育てることができる教師陣です。
安心して利用できる!
指導状況を把握できる指導報告書や教師交代など様々なサポート体制を整えております。オンライン家庭教師が初めての方でも安心してご利用いただけます。また、料金は完全後払い制で毎月指導を行った分だけ指導料をお支払いいただきます。教師交代費、授業キャンセル料、解約費、更新費、再入会費、兄弟/姉妹入会費はすべて0円です。
学習コーチコースのご案内
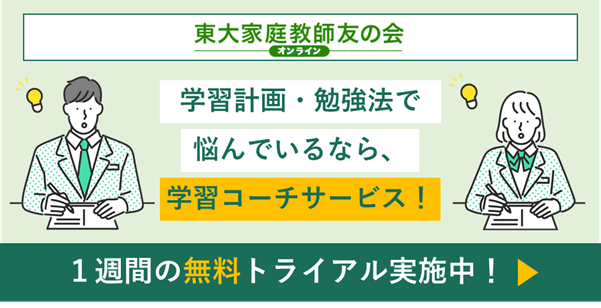
「そろそろ受験勉強始めなきゃとは思ってるけど、進め方が全然わからない…。」
「この勉強法で本当に合格できるかすごく不安…。」
「一人じゃだらけちゃって、勉強が進まない。」
そんなお悩みに、学習コーチが答えます!
実際に難関大学に合格した先輩が、あなたの学習計画・勉強法にアドバイス!
毎日チャットで勉強の管理も行います!
1週間の無料体験指導も実施しておりますので、ぜひお試しください。

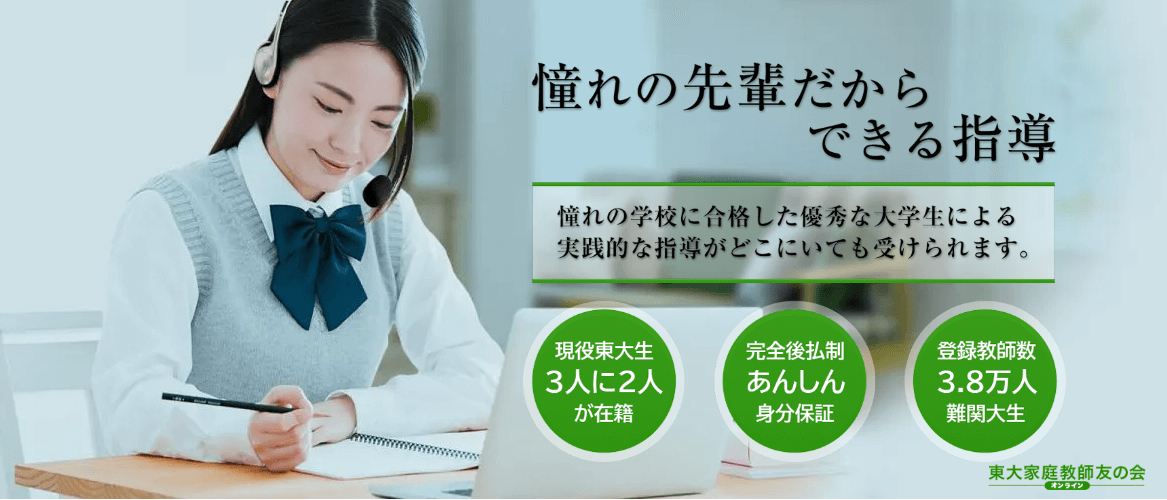
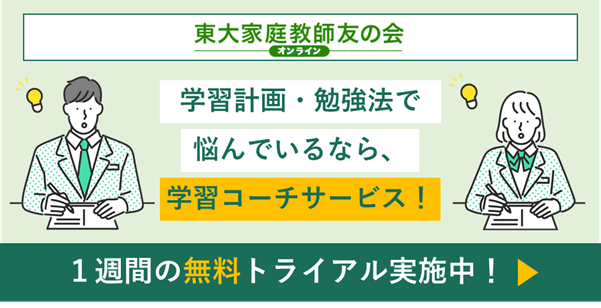
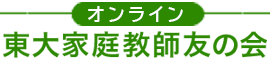


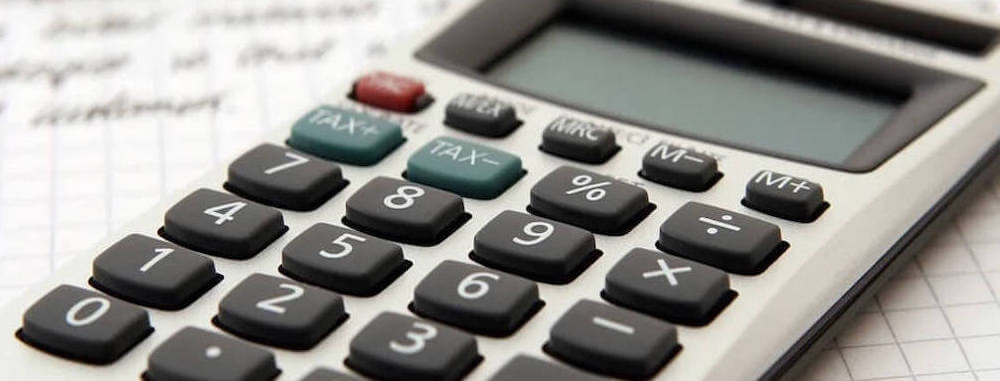


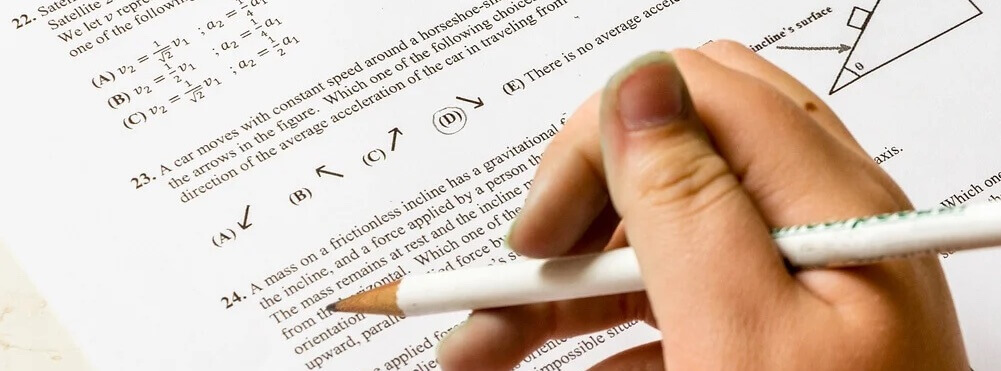



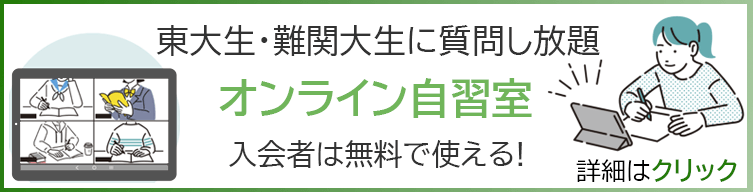
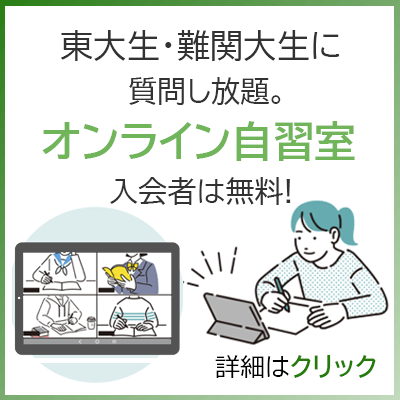
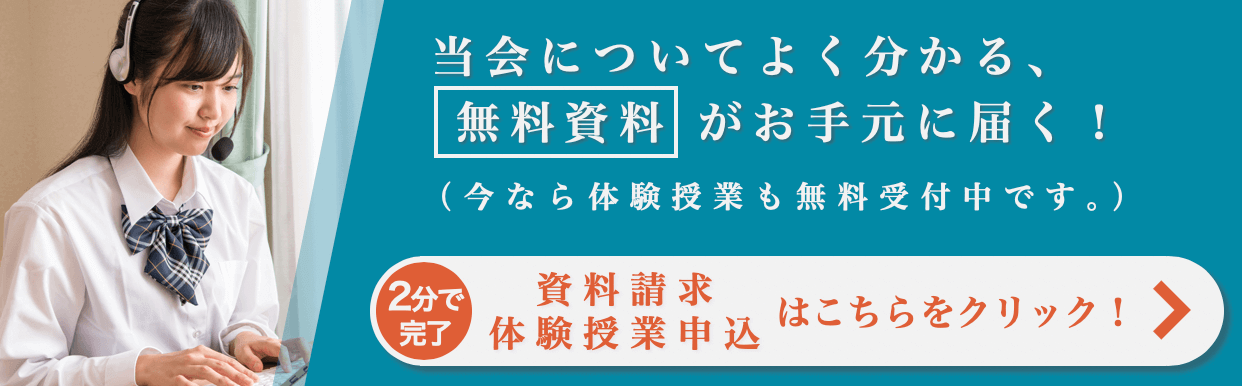
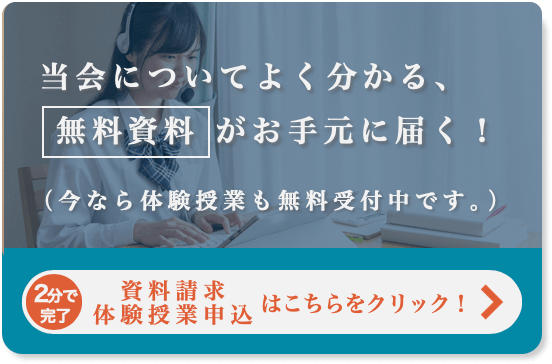
偏差値が全然届かず模試でもE判定続きで本当に自分が受かるのか、このままで受験に間に合うのかと不安でいっぱいの人もいるかと思います。私も、6月頃はE判定しか出たことがなく、数学の過去問を初めて解いたときは1割ほどしか取れませんでした。しかし、諦めずに1年間粘り続けたことで無事に合格することができました。
なかなか点数が伸びなかったとしても、確実に自分の力になっているのでいつか必ず伸びる時がきます。そのタイミングは人によってさまざまですし、すぐに伸びるということは珍しいので結果が出るまでには時間がかかるかもしれません。しかし自分がやってきたことを信じて最後の最後まで目標は高く持ち、頑張ってください。
あとは、心の状態は勉強にも大きく影響を与えるので、睡眠をしっかり取り、美味しいものを食べて、休むときはしっかり休むことを大切にしてください。もちろん勉強時間を多く取ることも大切ですが、メリハリをつけて休むことも大切なので忘れないようにしてください。応援しています。