
こちらのページでは、九州大学の入試を突破した現役の学生により、入試科目と試験時間・配点、各科目の傾向と対策が記載されています。
九州大学の入試を受けることを考えている高校生の方々は、現役学生による信憑性の高い情報を活かし、今後の受験勉強に役立てましょう。
九州大学の科目別入試傾向と対策
現役の九州大学の学生の経験から、各科目の入試傾向と対策をお伝えします。高い信憑性に基づく情報をご覧ください。
執筆者:九州大学経済学部の現役学生家庭教師のH.S先生
国語の傾向と対策

問題構成
出題科目が学部ごとに異なります。
まず、文学部は現代文一題と古文二題、漢文一題の出題です。次に、教育学部と経済学部経済・経営学科と法学部は現代文二題と古文一題、漢文一題の出題です。最後に経済学部経済工学科は現代文二題の出題です。
解答時間は文学部、教育学部、経済学部経済・経営学科、法学部が120分間、経済学部経済工学科が80分間となっています。
文学部と教育学部、経済学部経営・経営学科、法学部の現代文一題と古文一題と漢文一題では題材とする文章は共通していますが、一部の設問で異なる出題がみられます。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
国語の問題全体を通して多くの記述量を要求され、スピーディーな解答が求められます。
また、2024年度までは80字程度の字数制限のある設問が出題されていましたが、2025年度は全ての設問で字数制限は無くなりました。
現代文は1題につき、設問が6〜8問出題されます。すべての設問が記述式の問題です。古文・漢文は毎年3問程度の現代語訳と、文学史も出題されます。
文章の抽象度の高さ、設問の難しさ、記述量の多さを考えると国語の難易度は高いといえます。100点から125点を目安に目標得点を設定しましょう。
全体的な対策のポイント・注意点
教育学部、経済学部経済・経営学科、法学部の場合一題当たりの解答時間の目安は現代文35〜40分、古文、漢文は20〜25分です。じっくりと悩む時間はなくどんどん次の設問に回答していくようにしてください。空欄を残してしまうのは非常にもったいないため、とにかく全問解答する意識を持つことが大切です。
時間内に解けるようにするために、先に設問に目を通しておき、本文にマーキングしながら読み進めると良いです。本文を何度も繰り返し読むことは避けましょう。
また、過去問を解く際は、各設問の解答欄の大きさを参考にしてどの程度の文字数を記述する必要があるのか把握するようにしておくことをおすすめします。
各問題の対策のポイント・注意点
現代文では各設問100字程度の量の記述でもキーワードを抑え3〜5分で解答できるようにしましょう。
古文・漢文では現代語訳の問題が頻出です。丁寧に品詞分解して完答できるように単語、文法、句形をしっかりと抑えましょう。
また、文学史では時系列の理解を必要とする、難易度の高い出題があります。ここは時間をかけて時系列を整理し確実に得点するようにしましょう。
最後に国語の試験日は二次試験二日目の一時間目です。前日の英語・数学の出来にかかわらず切り替えて国語の試験に臨むようにしましょう。
英語の傾向と対策

問題構成
大問五題構成で大問1〜3は長文問題、大問4〜5は英作文です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
大問〜3は500字程度の文章が出題されます。設問の説明文は基本的に日本語ですが、年度によっては英語で出題されることもあります。
英作文については近年は自由英作文が2題出題されていますが、少し前までは和文英訳が出題されていました。今後も和文英訳が出題される可能性は十分にあるため、自由英作文・和文英訳ともに偏りのないように対策することが大切です。
長文問題の難易度は共通テストで80%以上安定してとれる実力があれば十分解答できるレベルです。ただし自由英作文は細かい専門知識を必要とするテーマや現在の社会問題を反映したテーマが出題されることが多く、対策が難しいです。
また、全体を通しては時間制限が厳格で難しいです。さらに、およそ5年に一度、英作文の代わりに要約問題が出題されています。英文要約の難易度はそこまで高くありませんが、過去問を利用して必ず対策しておくようにしましょう。
全体的な対策のポイント・注意点
制限時間は大問五個で二時間となっています。
時間配分は長文問題一題25分程度、自由英作文一題15分程度を目安に回答するように意識しましょう。
多くの設問が記述形式で、時間制限が厳しいので詰まらずにどんどん次の問題に進むことも意識してください。また、高度な構文や英単語はあまり出題されないので基礎事項をしっかり定着しておくことが大切です。
各問題の対策のポイント・注意点
設問が英語で出題された場合、問題の難易度が上がり平均点が下がる傾向にあります。
また、英文要約問題はここ数年出題されていないので、逆に入念な対策が必要です。この要約問題についても22分程度を目標に時間設定をしておくとよいでしょう。
英文要約は問題文にも記載されていますが、言い換えを意識することが大切です。英文をそのまま自分の解答として引用するのではなく単語を変える、言い回しを変える、などの工夫が求められます。そのためにも単語を覚える際には、動詞のニュアンスの違いまで深く理解しておくようにしましょう。
数学(文系)の傾向と対策
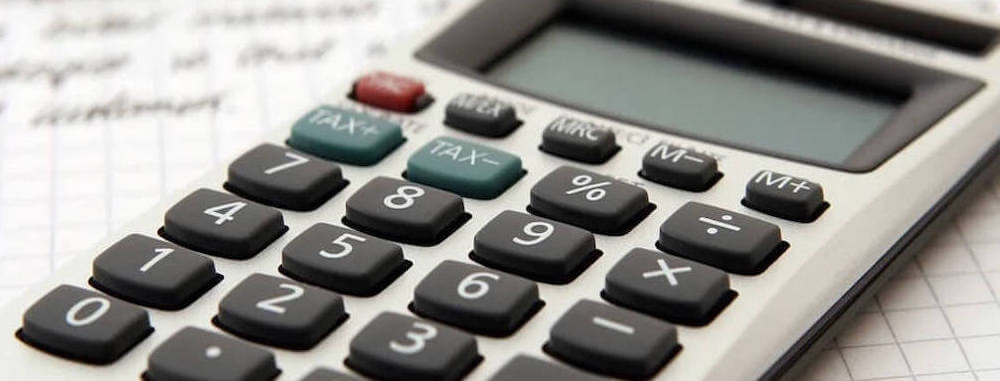
問題構成
大問4題構成です。
2025年度の出題は小問が少なく、各大問あたり一問の設問が多かったのですが、例年は各大問に数問の小問があります。時間は英語と同じく2時間で一問あたり30分が目安です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
理系との共通問題は年度によって誤差がありますが1〜2問程度で、その他の問題は文系だけの出題となっています。ただし、共通問題も一部の小問門は理系の問題と異なることがあります。
頻出分野としては微分・積分、ベクトル、数列、確率です。複数分野が融合した問題が出題されることもあります。
試験時間中の時間の使い方については、まず5〜10分ほどで問題すべてに目を通し、把握するようにしてください。その際、解答方針がすぐ立つ問題があれば、焦らず丁寧に解答することを心掛けて20分程度で解答するようにしましょう。
もしわからない問題があれば10分ほど手を動かしてみて、それでもらちが明かなそうなときは次の問題に進みましょう。ただし解答の「足跡」は丁寧に順序だてて記すことを心掛け白紙の答案を出さないようにすることも大切です。
全体的な対策のポイント・注意点
年度差はあるものの、基本的に共通テストで合格者平均程度の点数を記録することができれば、二次試験の数学で6〜7割程度の点数を獲得することで十分に合格点を狙えます。
ただし問題の難易度の乱高下が激しいため、「解ける問題を確実にとる」という意識が重要です。
また、公式の証明を求められる出題がされることもあります。教科書などを用いて本質的な意味を理解し、導出ができるようにしておきましょう。
各問題の対策のポイント・注意点
ベクトルに関しては、計算が複雑になることが多く、正確に解答を出せるのかがポイントになります。
また、微分積分に関しても同様に複雑な面積計算を求められることが多く、こちらも正確な手順と計算力が求められます。この際、「六分の一公式」や「十二分の一公式」、「三十分の一公式」を利用しないと解答が難しい問題もみられます。
公式を使いこなせるようしっかりと対策しておきましょう。
執筆者:九州大学医学部の現役学生家庭教師のS.N先生
数学(理系)の傾向と対策
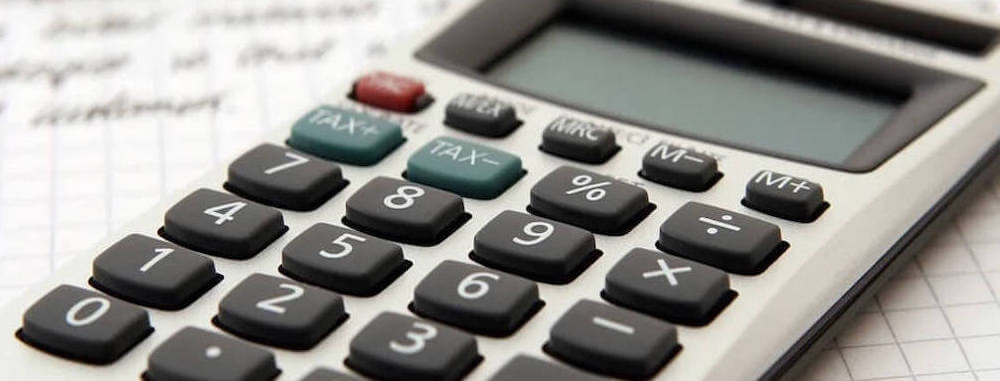
問題構成
大問5問構成、各大問に小問3問程度です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
積分を用いた面積、体積の計算や複素数平面、整数、確率が頻出です。
微積や確率は標準的な難易度で出題されます。複素数平面や整数はやや難易度が高く、手ごわいことが多いです。
また、2025年度入試では、2001年ぶりに図形の性質が基礎的な難易度で出題されました。全体の難易度としては、近年まで難化の一途を辿っていましたが、ここ数年はかなり易化しています。
2025年度は全体的にかなり易しかったため、その分かなり合格最低点も上がりました。難易度にかかわらず、「ほかの受験生よりも多くの点を取りに行く」ということを常に意識しておくことが大切です。
全体的な対策のポイント・注意点
制限時間に余裕はありますが、問題の解法を体系的に習得しておくことが求められます。
九大の理系数学は、数学Ⅲ・Cの出題が多く、計算量が非常に多い問題も散見されるため、どのような解法をとるのかをなるべく早く考え、手を動かして見通しをもって進めていくと良いでしょう。
筆者がおすすめする対策方法は、解けなかった問題を集め、その解法をなぜ選択するのが良いのかを考えてまとめたり、どのように立ち回って思考すれば良いのかをノートにまとめることです。こうすると本番でも焦ることなく、問題を解くことができます。
九大理系数学は標準的な問題を確実に解く力が求められます。基礎・標準の問題の載った参考書を完璧にし、知識を体系化しましょう。
過去問演習を行う場合、2006年以前と、2007年〜2020年までの問題、2021年〜2024年の問題の難易度が全く異なるので注意してください。なお、2025年は時間を測ってしっかりと演習するには向いていません。過去問以外にも演習問題が欲しければ、同じレベルの他大学として東北大学、北海道大学、名古屋大学の過去問もおすすめです。
各問題の対策のポイント・注意点
ここでは分野ごとに対策を書いていきたいと思います。
確率や微積は標準的な出題が多いので、過去問で必ず練習をしておきましょう。特に確率で解法の糸口が見つからない場合は、確率漸化式を疑って試行錯誤するとで議論が進むかもしれません。
また、整数や複素数平面は難易度がやや高いので、九大よりもレベルが高い大阪大学や京都大学、東京科学大学の問題に触れておくとより万全です。
医学科志望の方には、2019年の旧東工大の問題に、2017年に九大で出題されたものより難易度が高い類題があるのでおすすめです。さらに論証問題がかなり難しかった時期もあり、例えば、2019年の複素数平面の問題や2010年の論証問題です。こちらもぜひ実力試しに解いてみてください。
最後に、九大の教授曰く、九大理系数学はおおよそ難易度順に問題が配置されているそうです。そのため、自分の苦手分野を考慮しつつ、最初から順に解いていくことをおすすめします。焦らずに、着実に解いていくようにしましょう。
物理の傾向と対策
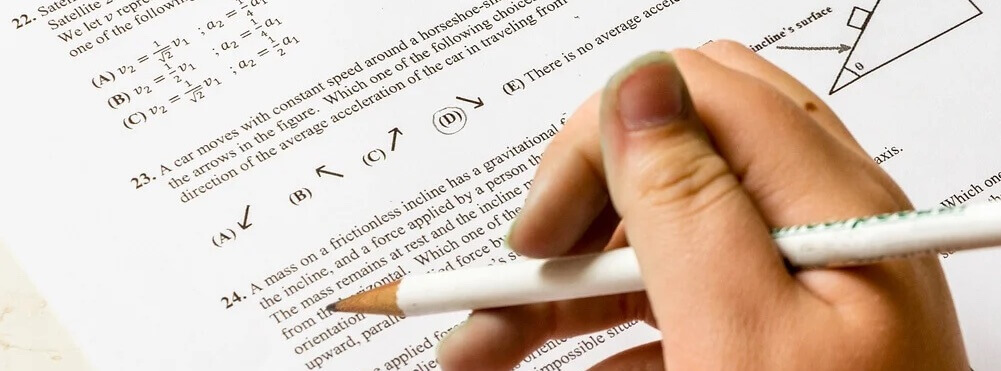
問題構成
大問は3問構成です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
主に記述式で解答のみを書く問題で、近年は数問、理由説明問題も出題されています。
例年、大問1は力学、大問2は電磁気、大問3は熱力学か波動から出題されます。ただし、2017年のように原子分野の知識が入った融合問題が大問3に出題されることもあります。
力学は単振動が、電磁気は導体棒の運動が、熱力学は熱機関が、波動は光の干渉が頻出です。難易度は標準的、で名門の森や入試物理の核心レベルが解けると十分対応できるでしょう。
複数のテーマから出題されることもあるので、特定の分野に偏らず広く正確に知識を身につけておくことが大切です。
全体的な対策のポイント・注意点
化学(生物)との兼ね合いを考えると、基本的には75分で解けるな時間配分を行いしましょう。標準的な問題がゆえに学部問わず、物理で大きな差がついてしまうことがあります。
九大は典型的な問題から少し外れたような問題を好みます。九大の過去問はもちろんですが、北海道大学の問題を解くことも強くおすすめします。実際、2025年度の大問2の積分を用いた問題は数年前の北海道大学の問題に非常に似ていました。また、他の旧帝大の問題を解くことも演習になるので、ぜひ演習してみてください。
各問題の対策のポイント・注意点
大問1(力学)は配点が大きく、最初に解くことが多い問題なので、次元解析や極端な値を入れて検証するなど検算を積極的にしていきましょう。
大問2は電磁気の知識があれば、比較的解きやすい問題です。標準問題を根気強く演習し、スムーズに解けるようにしておきましょう。
大問3は例年、熱力学と波動が交互に出題されます。去年の問題だけで決めつけず、どちらの分野も対策しておきましょう。
熱力学は、pv図や熱効率の知識をまとめましょう。必要なら、積分の知識を用いる早稲田大学や北海道大学の類題を探してみるのもよいでしょう。
波動はまんべんなく出題されるので、苦手意識を持たず、積極的に演習していきましょう。
最後に、頻出とは言えませんが筆者としては、原子分野も軽く対策しておくこともおすすめします。特に約30年前までは、ブラック反射やコンプトン散乱などが頻出で、やや難易度の高い出題もみられました。
化学の傾向と対策

問題構成
大問5問構成です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
解答のみの記述式です。理論、無機、有機、高分子とまんべんなく出題されます。
ここ10年程は、大問5で、アミノ酸と糖類が交互に出題されています。決め打ちせず、どちらの分野も対策しておきましょう。
近年は、標準電極電位やフィッシャー投影図など、受験生があまり見たことがないようなハイレベルな出題がされていますが、問題全体の難易度はおおむね標準的です。レベルとしては、重要問題集レベルが中心で、筆者が思うには良問が多いので、重要問題集に掲載されている問題を解くことができれば問題ないでしょう。
全体的な対策のポイント・注意点
物理(生物)との配分も考え、基本的には75分で解ききれるようにしましょう。全体を確認、解けそうな問題から手を付け、難しい問題は、一通り解き終わってから戻って解くことをおすすめします。
他の受験生も解ける問題を取り切ることが最も大切です。重要問題集やセミナーを繰り返し解いて、素早く正確に問題を解く力を身につけましょう。
また、九大化学は計算力を要する問題も多いため、普段から電卓に頼らず計算問題の演習もしっかりとおこないましょう。余裕があれば、計算問題によく出る値(酸性雨はpH5.6以下、食酢の質量パーセント濃度は4%程度など)を覚えておくと検算になります。
各問題の対策のポイント・注意点
無機化学は一度覚えてしまえば、ほぼ満点が取れるようになるので、完璧に覚えるようにしましょう。友達と沈殿の色などの無機分野の問題を出し合ったり、語呂合わせを共有したりして、知識の穴を埋めていきましょう。
理論化学はやや難しい問題もありますが、知識と解法をあわせて覚えていくようにしましょう。
有機化学はほとんど構造決定問題が頻出です。やや難易度が高いので、過去問を繰り返し解き、どのように物質を同定していくのかを定着させましょう。
近年大問5は、思考力を問う問題が増えています。九大よりもレベルの高い大阪大学の問題を、数年分解いておくと安心です。
最後に、共通テスト化学と並行して二次試験の演習をすると、共通テストの問題演習の速度も上がるので、ぜひ取り組んで見てください。
執筆者:九州大学農学部の現役学生家庭教師のI.H先生
生物の傾向と対策

問題構成
例年、大問5問構成。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
5問それぞれ異なる分野から出題されます。毎年出題分野に大きな偏りはありませんが、強いて言うなら、光合成と呼吸、進化の分野が頻出です。
問題の形式は、選択、記述、計算、論述、空欄補充など多様です。特徴的なのはどの大問にも必ず語句の穴埋め問題が出題されるということです。この穴埋め問題では、非常に基本的な内容で、基礎的な語句をしっかりと身につけられているかが問われます。
難易度は、全体的に標準レベルです。旧帝大といわれる難関大学のレベルと比べると易しい問題が多いでしょう。
時間は理科2科目で150分のため、目安としては70分〜75分で解きたいところです。しかし、年度によって記述や選択問題の出題量にばらつきがあるため臨機応変な対応力が求められます。
全体的な対策のポイント・注意点
まず対策が必要なのは記述問題です。各大問に一つ以上、100字を超える記述問題が出題されることも珍しくありません。
記述の内容は、①教科書レベルの語句の意味を問う問題、②すこし複雑な知識がいる問題、③多くの受験生が初めて見る実験問題の結果を考察してそれを記述させられる問題と大きく3つあげられます。よって、時間をかけずにすぐに書き出さなければならない記述と時間をかけるべき記述の2つのパターンを見極めることが重要です。特に語句の定義だけを答える記述はいかに早く仕上げるかがカギになります。
また、できるだけ多くの問題に触れて経験値を上げることが大切です。ほとんどの人が解けないようなレベルの問題は出題されないため標準レベルの問題を確実に解く練習を普段から多くしていきましょう。
各問題の対策のポイント・注意点
全ての大問に出題される穴埋め問題は最低でも8割は正解できることが望ましいです。教科書レベルの単語がほとんどなので、普段から語句と定義を覚えることは欠かさずに行いましょう。穴埋め問題対策は一問一答形式の参考書がおすすめです。
また、初見の実験問題が出題されることを想定しておくことも大切です。
対策としては、参考書や模試などで出てくる初めて見る問題を丁寧に扱うことです。すぐに答えを見るのではなく、じっくり考える癖をつけ、それでもわからなかった場合は解説を熟読しましょう。なぜその回答にたどり着けなかったのか、どうしたらその回答にたどり着けていたのか、を徹底的に分析することがポイントです。
この積み重ねで初見の実験の問題に対する対応力が伸びていきます。初見の問題の練習は初見の問題でしかできないということを念頭に置いておきましょう。
オンライン家庭教師で
九州大学に合格!
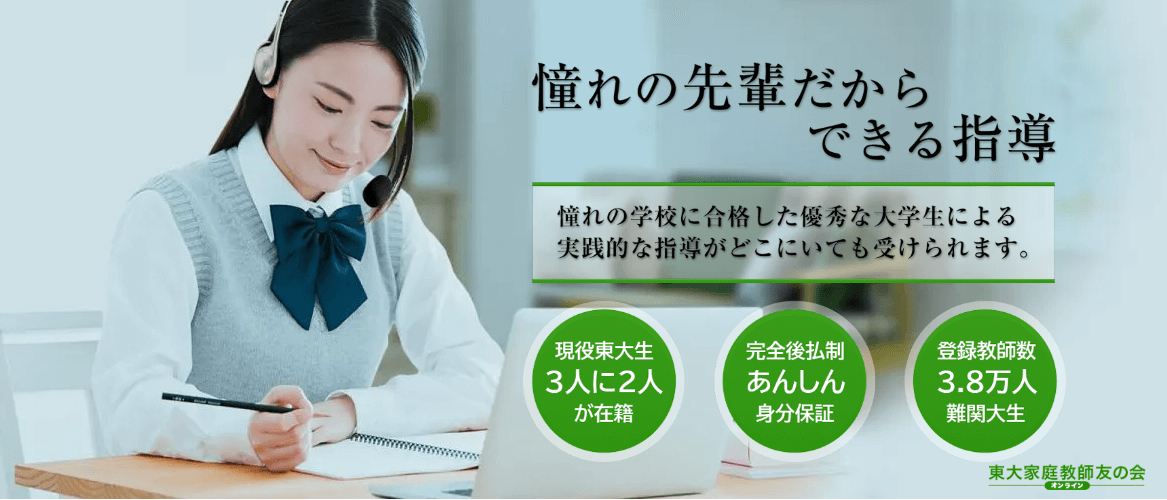
オンライン東大家庭教師友の会は、3.8万人の難関大生家庭教師が在籍する、オンライン家庭教師サービスです。
オンライン指導のため、北海道〜沖縄まで全国どこからでも難関大生による質の高い指導を受けることができます。
無料の資料請求や無料の体験授業を実施しておりますので、ぜひお試しください。
九州大学の学部/学科別の前期日程入試科目・配点
以下、入試科目・配点等の情報は全て「令和8(2026)年度入学者選抜概要」より抜粋しています。最新の入試情報は、九州大学HP等でご確認ください。
共創学部
共通テスト・配点合計525点
国語100点
地歴公民(200点)※1
数学100点
理科(200点)※1
外国語100点
情報25点
※1 「地理歴史及び公民」及び「理科」の成績は,合計300点満点を200点満点に換算して利用します。
個別学力検査・配点合計1000点
数学300点
外国語400点
小論文等300点
文学部
共通テスト・配点合計275点
国語50点
地歴公民50点
数学50点
理科50点
外国語50点
情報25点
個別学力検査・配点合計500点
国語150点
地歴公民100点
数学100点
外国語150点
教育学部
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民100点
数学100点
理科50点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計600点
国語200点
数学200点
外国語200点
法学部
共通テスト・配点合計350点
国語50点
地歴公民100点
数学50点
理科50点
外国語50点
情報50点
個別学力検査・配点合計600点
国語200点
数学200点
外国語200点
経済学部経済・経営学科
共通テスト・配点合計475点
国語50点
地歴公民200点
数学50点
理科50点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計600点
国語200点
数学200点
外国語200点
経済学部経済工学科
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計750点
国語150点
数学300点
外国語300点
理学部物理学科/化学科/地球惑星科学科/数学科/生物学科
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計700点
数学250点
理科250点
外国語200点
医学部医学科
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計700点
数学250点
理科250点
外国語200点
医学部生命科学科
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計800点
数学250点
理科250点
外国語200点
面接100点
医学部保健学科看護学専攻
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計400点
数学100点
理科100点
外国語200点
医学部保健学科放射線技術科学専攻
共通テスト・配点合計500点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報50点
個別学力検査・配点合計700点
数学250点
理科250点
外国語200点
医学部保健学科検査技術科学専攻
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計700点
数学250点
理科250点
外国語200点
歯学部
共通テスト・配点合計475点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報25点
個別学力検査・配点合計700点
数学250点
理科250点
外国語200点
歯学部創薬科学科/臨床薬学科
共通テスト・配点合計500点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報50点
個別学力検査・配点合計700点
数学250点
理科250点
外国語200点
工学部
共通テスト・配点合計520点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報70点
個別学力検査・配点合計700点
数学250点
理科250点
外国語200点
芸術工学部芸塾工学科
共通テスト・配点合計550点
国語100点
地歴公民100点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報50点
個別学力検査・配点合計750点
数学250点
理科250点
外国語250点
農学部
共通テスト・配点合計500点
国語100点
地歴公民50点
数学100点
理科100点
外国語100点
情報50点
個別学力検査・配点合計750点
数学250点
理科250点
外国語250点
オンライン東大家庭教師友の会が選ばれる3つの理由
ハイレベルな教師陣!
当会に在籍する家庭教師は全て難関大生または難関大卒であり、彼らは受験事情に精通し独自の勉強法やノウハウを持っています。また、採用率20%の厳しい選考を行い、教師としての指導力・優れた人間性・指導の戦略性を持った人材のみを採用しています。オンライン東大家庭教師友の会の教師の質は国内トップクラスです。
相性のいい教師が見つかる!
当会には38,000名の現役難関大生やプロの講師が在籍しています。教師数が多いということはそれだけ多くの教師を選べるということです。学習状況や希望する教師条件のヒアリングと、厳格で緻密な選考を通して、お子様にぴったりな教師をご紹介します。生徒の「勉強をしたい」という気持ちを育てることができる教師陣です。
安心して利用できる!
指導状況を把握できる指導報告書や教師交代など様々なサポート体制を整えております。オンライン家庭教師が初めての方でも安心してご利用いただけます。また、料金は完全後払い制で毎月指導を行った分だけ指導料をお支払いいただきます。教師交代費、授業キャンセル料、解約費、更新費、再入会費、兄弟/姉妹入会費はすべて0円です。
学習コーチコースのご案内
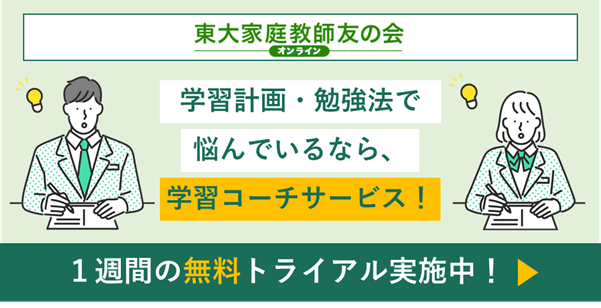
「そろそろ受験勉強始めなきゃとは思ってるけど、進め方が全然わからない…。」
「この勉強法で本当に合格できるかすごく不安…。」
「一人じゃだらけちゃって、勉強が進まない。」
そんなお悩みに、学習コーチが答えます!
実際に難関大学に合格した先輩が、あなたの学習計画・勉強法にアドバイス!
毎日チャットで勉強の管理も行います!
1週間の無料体験指導も実施しておりますので、ぜひお試しください。

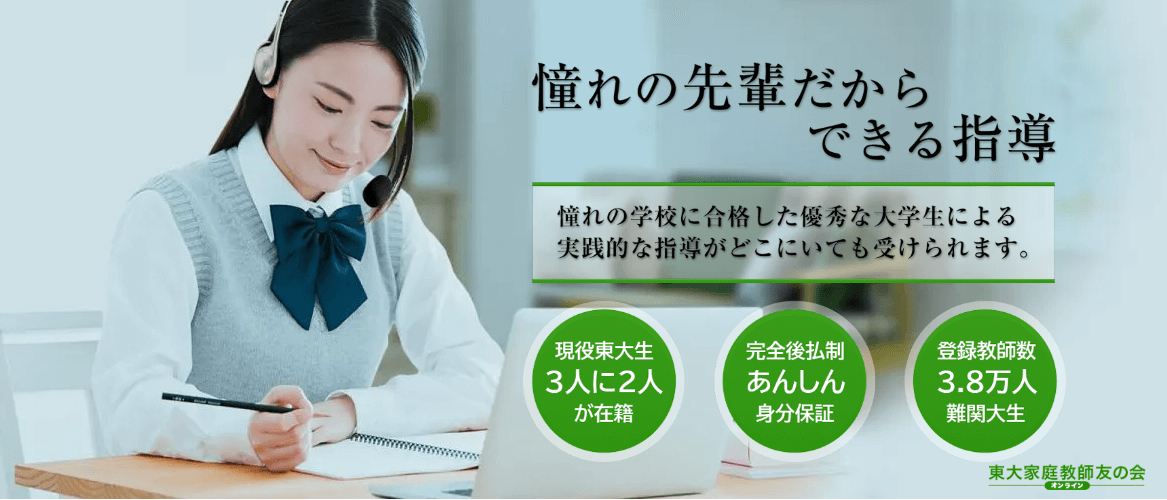
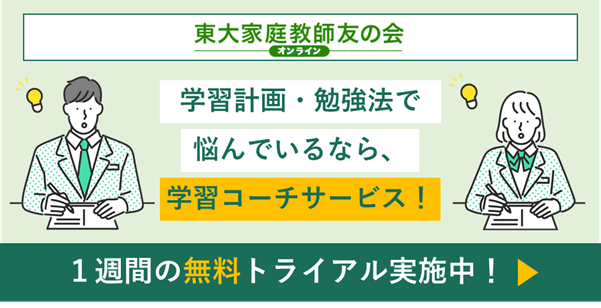
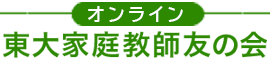



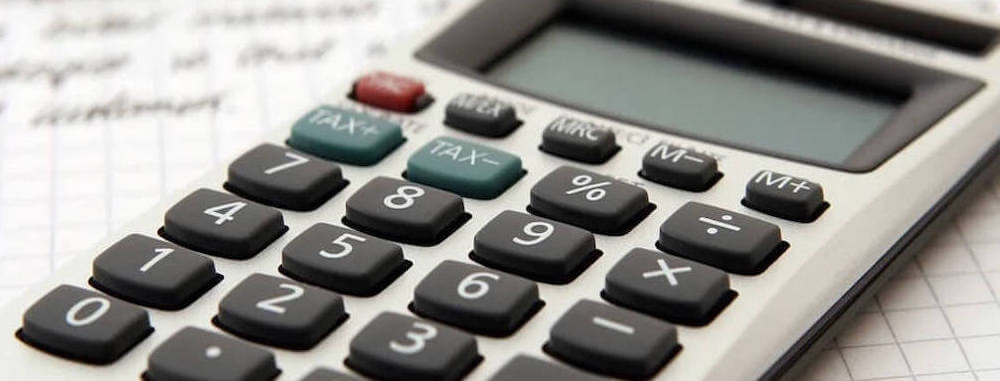
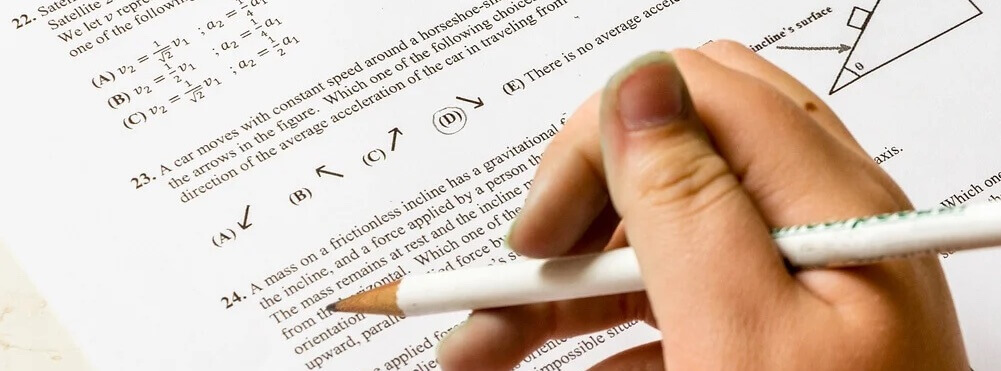


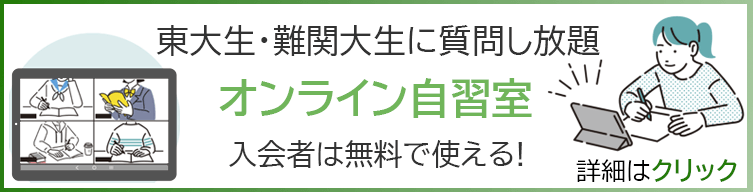
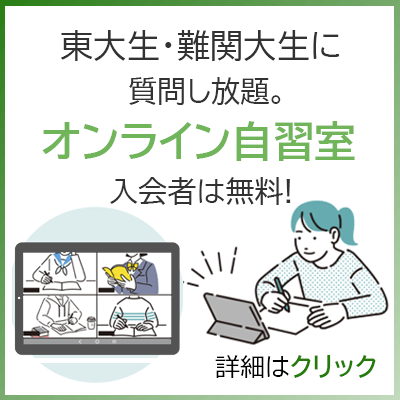
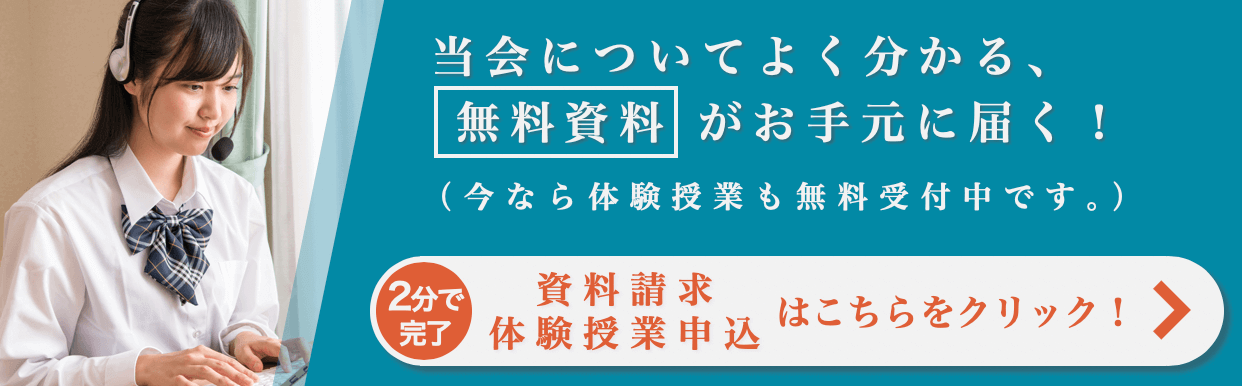
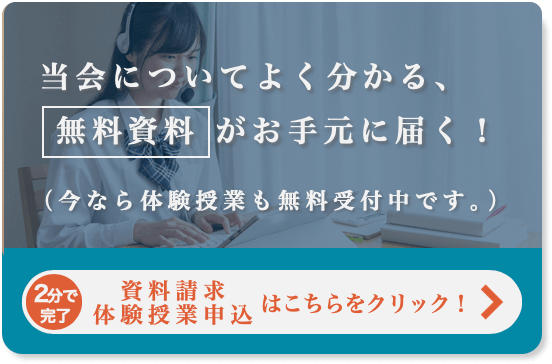
九州大学は二次試験の問題が難しいものの、しっかりと基礎から積み上げて勉強した受験生が報われるような出題になっています。そのため、焦らずに地道に学習を継続することが大切です。
また、各予備校が実施する九州大学模試を絶対に受験することをお勧めします。筆者は模試の主な対策として、過去問を模試を受験する前に一度絶対に解いておくことと、模試を受験するまでの期間に学習した授業の復習と参考書の復習を行うようにしていました。その結果、九州大学の模試で三科目偏差値76.8を記録しました。
ものすごく単純なことのように思われるかもしれませんが何度も基礎的な問題や暗記事項に取り組むことで模試で絶対に間違ってはいけない問題を正解できるようになり、おのずと成績は上昇していきます。
また、可能であれば複数の模試を受験することもおすすめします。基本的に合格者は英語で130点程度、国語は115点程度を記録しています。数学は年度によって難易度がかなり異なり、点数のブレがものすごく大きな科目であるので、英語と国語の点数を安定させたうえで数学の対策に臨むことがポイントです。
最後になりますが、みなさん受験勉強がうまく進み、良い知らせが届くことをお待ちしております。