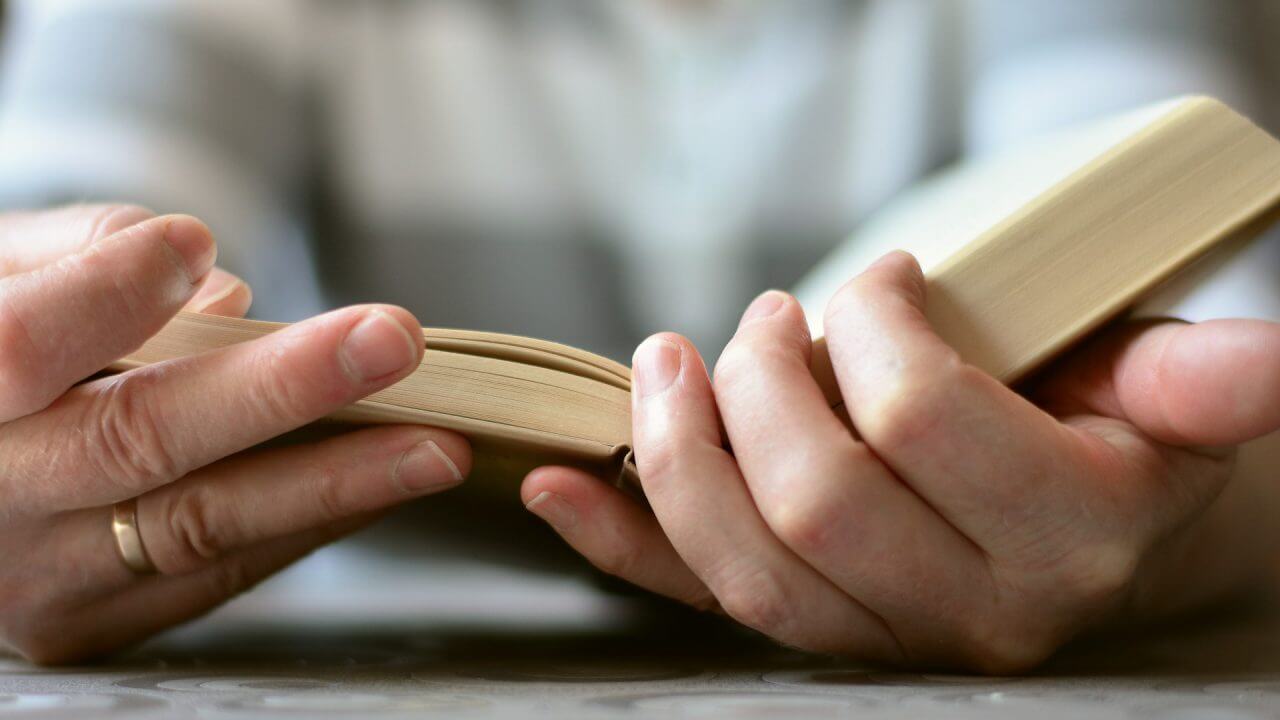
こちらのページでは、京都大学の入試を突破した現役の学生により、入試科目と試験時間・配点、各科目の傾向と対策が記載されています。
京都大学の入試を受けることを考えている高校生の方々は、現役学生による信憑性の高い情報を活かし、今後の受験勉強に役立てましょう。
京都大学の科目別入試傾向と対策
現役の京都大学の学生の経験から、各科目の入試傾向と対策をお伝えします。高い信憑性に基づく情報をご覧ください。
執筆者:京都大学文学部の現役学生家庭教師のN.S先生
国語の傾向と対策

問題構成
例年、現代文は随筆調の文と論説調の文が各一題、古文が一題出題されます。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
文理によって多少の差はありますが、現代文は基本的に三行から五行程度の記述問題が五問ほど出題されます。三行程度の問題は、本文を読めていれば解くことができるものも多いです。小問五などは記述量が多く、難度も高いです。本文に明確な答えがなく、自分で考えて記述する力を問うものもあります。また、文章のテーマも様々です。初めて見るテーマでも動じず、普段どおり読解をこなすのが大切です。
古文は、内容理解や現代語訳の記述問題が出題されます。行数は二行から四行程度であることが多いです。現代語訳が出来ていれば対応できる問題が多く、現代文に比べれば難度は低いため、得点源にしたいところです。
全体的な対策のポイント・注意点
まず、記述問題については添削を積極的に受け、反省点を次の解答に活かしましょう。この際に下書きも一緒に見せると、思考過程から振り返ることができます。答案前の下書きはとても重要です。問われていることに答え、論理の飛躍なく丁寧に追いかけた下書きを書けるようになりましょう。復習の際は、下書きまででとどめておくと時間短縮になります。
各問題の対策のポイント・注意点
現代文は、記述量が多く、比較的ゆったりと書ける傾向にあります。そのため、加点になりそうな要素をできるだけ多く文章に盛り込む能力が求められます。二文になってもよいので、書きたい要素をすべて詰め込む練習をしておきましょう。
古文については、助動詞などのポイントを押さえて現代語訳ができれば合格点を取ることができます。過去問の文章を品詞分解し、現代語訳してみるのがよいトレーニングになるでしょう。過去問集は、全訳がついているものを選ぶのがおすすめです。
世界史の傾向と対策

問題構成
世界史は、東洋史(中国、イスラームなど)から400字の論述問題が一題、一問一答が一題、西洋史から論述問題が一題、一問一答が一題となっています。この構成は長年変わっていません。年代については幅広く、古代から近現代まで出題されています。
また、2025年度からは資料読み取りや短文記述の問題が追加されました。こちらはさほど難易度は高くないため、落ち着いて自分の考えを書くことが大切です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
400字の記述については、「流れ」「比較」「影響」などをテーマにした問題が出題されます。条件が文章で細かく指定されるため、正確に読み取り、解答することが求められます。
一問一答については、単語帳に載っていないような語句も出題されますが、それ以外の基本的な単語で8割を目指すことができるでしょう。
全体的な対策のポイント・注意点
京都大学の対策においては、単語を「流れ」の中で覚えることがとても大切です。一問一答は文章の穴埋め形式ですし、論述問題でも特定の単語が得点条件となることが多いからです。ワークや単語帳で覚えられない単語があれば、教科書に戻って前後を読み返すといいでしょう。
また、因果などの「流れ」を意識して覚えることも大切です。教科書の記述で原因と結果に線を引くなどして情報を集約するのがおすすめです。
各問題の対策のポイント・注意点
一問一答では、答えとなる単語は基本的なものになりますが、京都大学特有の捻った聞き方をされるため、過去問を五年分は解き、慣れておくのが望ましいです。テーマは10年ほどは同じものが出題されない傾向にあるので、筆者は古い年度の過去問も解いていました。
論述問題は、様々なテーマから出題され、過去と同じ内容のものはほとんど出題されません。そのため筆者は冠模試の過去問や、一橋、東大など他大学の過去問も解いていました。歴史の流れを理解していることはもちろん、出題条件に従って論述を組み立てることが求められます。添削してもらうだけでなく、模範解答を分析し、いい書き方を学びましょう。
執筆者:京都大学法学部の現役学生家庭教師のT.A先生
英語の傾向と対策

問題構成
例年、長文2題と和文英訳、自由英作文がそれぞれ1題ずつの計4題構成。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
長文問題に関しては基本的に英文内の下線部の内容を和訳したり、日本語で説明したりすることが求められます。ただ、2題ともに設問内容は固定されておらず年度によって形式は頻繁に変わります。
和文英訳問題は難易度が高いといえます。日本語であっても一筋縄では理解できないような内容や、小慣れた日本語表現を英訳することが求められます。
自由英作文問題では、とあるシチュエーションで登場人物がとりうる表現を想像して英作文を作成することを求められることが多いです。
ただ、年度によっては解答者に対して意見を求める問題が出題されたり、長文問題の中に100字程度の自由英作文を求める問題が組み込まれたりするなど、出題形式には一定の傾向がなく、見通しが立ちにくいといえます。
全体的な対策のポイント・注意点
京大の英語入試問題はかなりハイレベルな英語力を受験生に対して求めます。また、出題形式も独特です。そのため、全体を通して言えることは単語力や文法力などを早い段階で身につけ、過去問を解いて京大独自の形式に慣れておくことが重要だということです。
しかし、出題形式が変わりやすいことも一つの特徴であるため、他大学の過去問にも取り組み、あらゆる問題に対応できる柔軟な力を養うことも大切です。
各問題の対策のポイント・注意点
長文問題は、文字数自体はそれほど多くないものの抽象的な文章が出題されることが多いため、単語はもちろんのこと文法や文同士の繋がりを理解する読解力が必要となります。
また、難単語が文章内に現れた際に、前後の文脈をもとにその意味を推測する力が必要です。
この力は過去問演習を積むことで鍛えることができます。
和文英訳問題についても、京大英語独特の問題に慣れるためには過去問演習で経験を積むことが大事です。その前段階として、『大学受験のための英文熟考』や『英文読解の透視図』などのハイレベルな参考書などで土台を作ってから過去問に臨むことで、より高い学習効果が得られるでしょう。
自由英作文問題については、問題数を多くこなすことが重要です。その際には、京大の過去問だけでなく他大学の過去問や参考書にも取り組みましょう。
また、英作文では自分でも気づかないクセがついてしまっていることもあるため、積極的に添削をしてもらうことをおすすめします。
日本史の傾向と対策

問題構成
基本的に全範囲から出題される史料問題、テーマ史問題、前提文問題、論述問題の4題構成。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
史料問題は文献史料からの出題で空欄補充や短答形式の問題となっています。
教科書・史料集だけでなく初見史料からの出題もあります。
テーマ史問題は短文の空欄補充形式の問題であり基本的には教科書レベルの単語の解答を求められることが多いです。
前提文問題は3つのリード文をもとに出題され、主に語句を答える記述問題と文中の空欄を補充する形式の記述問題によって構成されます。
論述問題は、例年論述テーマのみが提示されるシンプルな問題形式となっています。点数の差が開きやすい問題となっているため、しっかりと得点することが求められます。
全体的な対策のポイント・注意点
京大の日本史は原始・古代、中世、近世、近代・戦後の4つの時代区分からそれぞれ均等に25点分ずつ出題されます。また、多様な出題形式が取られていることも特徴です。
そのため、時代の流れを通して偏りなく、かつ深い理解を得る必要があります。
各問題の対策のポイント・注意点
大問1〜3は概ね基本用語からの出題となっているため、50点以上の得点を目指しましょう。
まず、教科書・図説資料集で全範囲を体系的に学習しましょう。その際に太字となっている重要な用語は漏らさずに覚えるようにしてください。
また日本史の全体像、現在に至るまでの流れを意識して把握することも大切です。
共テ対策に時間を取られる前に自分の手で年表を書いてみることをおすすめします。
教科書で全範囲を一通り押さえられたら演習に取り組みましょう。
史料問題は対策が必須です。特に初見史料については少ない手がかりからその史料が何を指しているのかを類推する力が求められます。
そのため、史料問題の参考書で解き方を押さえてから、過去問に取り掛かるのがおすすめです。
京大の出題形式に慣れると同時に、理解できていない箇所の洗い出しもするようにしましょう。
大問4の論述問題は得点差がつきやすく、20点以上を目指したいところです。
論述問題についても全範囲から出題されますが、特に問われやすい政治・社会経済史については重点的に対策しましょう。
論述問題では、教科書レベルの理解を前提として、その内容を論理的に文章化する論述力が求められます。
そのため、積極的に添削指導を受け、赤本の解答や先生による模範解答と自分の解答を見比べてより良い解答をリライトし、文章力・構成力を磨いていきましょう。
執筆者:京都大学法学部の現役学生家庭教師のM.Y先生
数学(文系)の傾向と対策
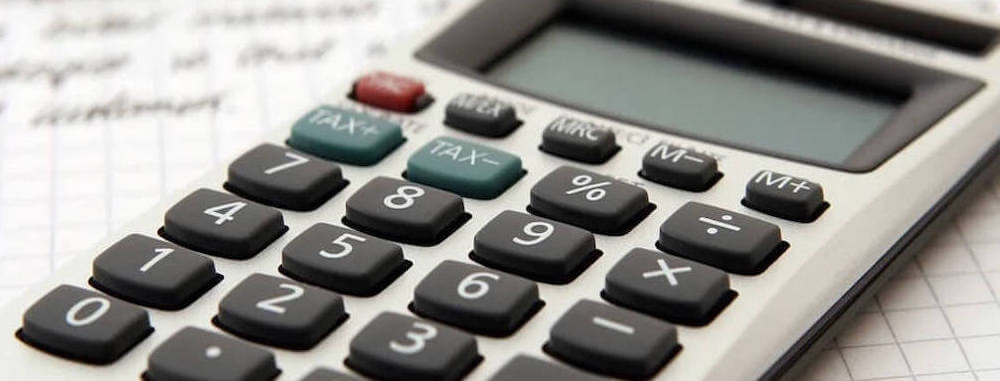
問題構成
京都大学の文系数学は大問5問構成、試験時間は120分で、全問が記述式です。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
京都大学の数学は、小問がほとんどありません。つまり小問による誘導がなく、大問一つにつき一問しかないことがほとんどです。
頻出分野は、微分積分、ベクトル、確率です。特に微分積分は、面積や体積を求める問題としてよく出題されます。確率では、漸化式と組み合わせた問題が多く、ベクトルは空間図形との融合問題として出題されることが多いです。これらの分野に加え、整数問題や図形と方程式なども幅広く出題されます。
全体的に高い難易度ですが、年度によっては取り組みやすい問題も含まれます。合否を分けるのは、難易度の高い問題に固執せず、確実に得点できる問題を見極める力と、部分点を積み重ねるための丁寧な記述力です。
全体的な対策のポイント・注意点
小問がほとんどないため、問題の誘導が少なく、自分で解法を組み立てる発想力や応用力が不可欠です。基礎的な知識はもちろん、初見の問題にも柔軟に対応できる力が求められます。過去問演習を通して出題形式に慣れ、時間配分を意識した対策が重要です。また、論理的な思考力を養うため、日頃から解答の過程を丁寧に記述する練習を重ねましょう。
各問題の対策のポイント・注意点
微分積分の問題では、問題の式を自分が解ける形の式に変形できるようにしましょう。式変形のやり方はひとつのパターンを覚えるのではなく、色々なやり方を手札として持っておくことが大切です。そして問題を解く際に、なぜそのやり方を選んだのか理解しながら使い分けられるようにしていきましょう。ベクトル、確率の問題は条件が複雑なことが多いので、内容を図や表に置き換えることを習慣付けてみてください。これにより、内容整理だけでなく、求めなければならない前提条件や考慮しなければならない条件が明確になり、記述の効率も向上します。
執筆者:京都大学理学部の現役学生家庭教師のK.Y先生
数学(理系)の傾向と対策
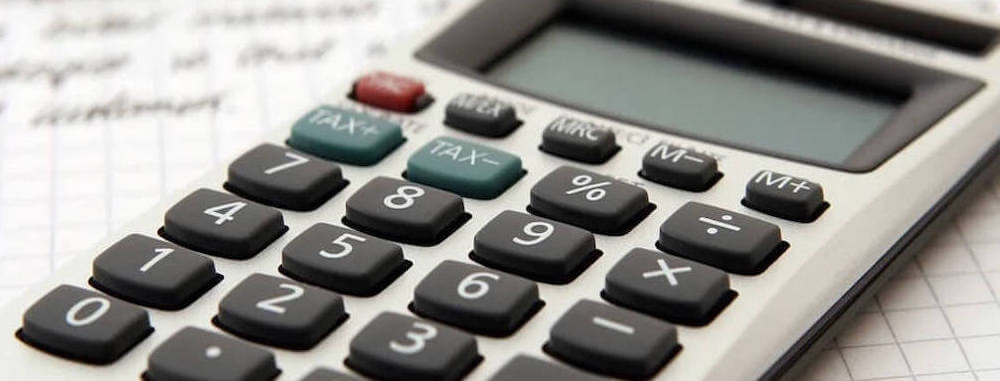
問題構成
京都大学の理系数学は大問6題で構成されています。試験時間は2時間30分のため、単純計算で1問当たり25分かけられるということになります。
大問1は小問集合の形式を取ることがあり、近年では2021年、2023年、2025年の入試で大問1が小問集合でした。その他の大問に関しては、「大問◯番ではこの分野の問題が出る」というような傾向は定まっておらず、毎年満遍なく高校数学のほぼ全範囲から出題されます。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
京都大学理系数学の大きな特徴は、誘導や小問が少ないということです。2025年入試では大問1と4以外では小問がありませんでした。そのため、部分点を取ることが難しい形式になっています
京都大学では数年間の周期で高校数学のほぼ全ての範囲を出題していますが、特に微積分、場合の数・確率、整数が頻出分野でこれらはほぼ毎年出題されているため念入りに対策しておく必要があります。
難易度に関しては2021年以降、比較的穏やかな出題が続いていましたが、2024年・2025年からは以前の難易度に戻りつつあります。しかしながら「極端に発想が難しく、試験時間中には解答不可能な捨て問」や「計算量が非常に多く試験時間中に計算しきれない問題」はほとんどありません。全体として、努力が得点に結びつきやすい試験と言えるでしょう。
全体的な対策のポイント・注意点
京都大学の理系数学では、まず計算ミスをなくし、チャートなどの基本問題を反射的に解ける状態にすることが重要です。高校2年生の終わり頃までには基本問題を解ける状態を目指し、その後、一対一対応の解法暗記から脱却していく必要があります。
初めて見る問題にどのように向き合うかということに焦点を当てて参考書を使い、対応力を身につけていきましょう。特に誘導がない状態でどのように解いていくのかを意識して、普段の演習に取り組むことが大切です。この出題形式は京都大学特有のもので、慣れておくことが不可欠です。
また京都大学の入試では計算ミスによって30点程も失点してしまうことがあります。換算後には50点近くの失点になる場合もあるので、普段から計算ミスをしないように対策することが必要になります。字や途中式を丁寧に書くことに加えて、演習や試験の中でやってしまったミスをノートにまとめ試験前、演習前に確認することが有効です。
また、解答用紙の右半分は計算用紙になっています。そこに乱雑に計算を書いていくのではなく、自分が見やすいようにある程度整理した形で計算をしていくことも大切です。
各問題の対策のポイント・注意点
整数問題の解法は大別して①余りで分類する②約数に注目する③必要条件を考え、範囲を絞り込むという3通りです。この3通りのうちのどれを選択するかを意識して問題を解いていると良いでしょう。
微積分に関しては計算を正確に行うことが非常に重要になります。特に現役生の場合、演習量が不足して計算ミスを頻発するという事態が起こりがちです。自分のしたミスをまとめる、計算練習は毎日やるという2点を意識して、本番でミスをしないようにしましょう。
また、京都大学で出題される数少ない「誘導付きの問題」は、教授たちが「誘導がないと受験生は解答不可能だと判断した」問題です。その場合は、提示された誘導に乗ることが非常に重要になります。誘導付きの問題についても、提示された流れやヒントにそって解く力を身につけておくのがよいでしょう。
生物の傾向と対策

問題構成
大問4問構成。
京都大学の理科は試験時間180分で、物理・化学・地学・生物の中から2科目を解くのが一般的です。そのため、生物にかけられる時間は90分程度になります。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
大問自体は4問ですが、それぞれの大問が(A)、(B)のように分かれていることがあり、実際には6テーマ程度を扱うことが多いです。そのため90分で全ての設問を解こうとすると時間が不足しがちです。どの設問も「教科書の一歩先を考察させる」という出題で、正確な知識と考察力、さらに実験などのリード文を読解する力を要求される非常に難しい問題です。
前半の2問は細胞や遺伝子などのミクロな話題を、後半の2問は進化・系統・生態系・個体群などのマクロな話題が出題されることが多いですが、毎年若干の変動があります。
特に「生物の進化」と「遺伝子発現」は頻出で、これらの分野は毎年必ず何らかの形で出題されています。生物という教科を理解する上でも非常に重要な単元なので、正しい知識を身につけ、考察できるようになることが大切です。
全体的な対策のポイント・注意点
京都大学の生物では、まず「教科書の知識を正確に身につける」ことが大前提となります。用語を穴埋めできる、説明できるというだけでは不十分で、その用語を実際に使えることや、教科書に出てきた反応の流れを利用して正しく推論できることが求められます。そのため、ただ暗記するだけではなく、知識の「質」を高める学習が不可欠です。また、考察問題は「日本一難しい」と言われるほど難易度が高いです。演習を通して生物の力をつけていくだけでなく、何とかして部分点を取るという練習も必要になります。
生物は時間が不足しがちです。1問に時間をかけすぎると、本来解けたはずの問題を落としてしまう可能性があります。問題をパッと見ただけで難易度を判断することは難しいため、少し解き進めて「時間がかかりそう」だと感じたら、すぐに埋められる知識問題だけを埋めて、次に進むという判断をした方が良いでしょう。
各問題の対策のポイント・注意点
ミクロ分野では、図を正確に書き、物質・反応の流れを図示できるかどうかが、その分野を理解しているかの目安となります。普段の学習では、面倒くさがらずに「図を書いてみる」ことが大切です。マクロ分野は、何となく理解したつもりになりがちであるため、ミクロ分野以上に用語とその意味を正しく理解し、正確に使えるようになるという訓練が重要です。
また、京都大学ではかなりの量の論述問題が出題されます。論述は自分で書くだけでは力がつきにくいため、身近な先生などに必ず添削してもらい、客観的な評価をうけましょう。
京大生物では難しい問題が出題されますが、結局求められていることは「教科書の本質的な理解」です。そのことを忘れず、基本に忠実に勉強していくことが最も重要です。
執筆者:京都大学理学部の現役学生家庭教師のS.Y先生
物理の傾向と対策
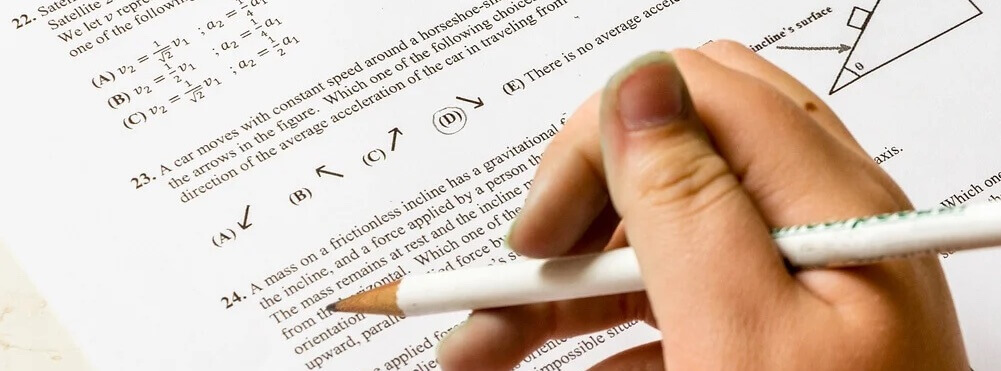
問題構成
京都大学の物理は、大問3題からなり、通常それぞれの大問は、長い文章によって誘導された10〜15問の穴埋めと2問ほどの記述問題で構成されています。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
力学では、円運動や単振動、運動方程式、力学的エネルギー保存則と仕事の関係、重心系から見た運動などの分野が頻出です。
電磁気学では、電磁気現象やキルヒホッフの法則、電磁誘導の法則が頻出であり、電荷保存や極版間引力、仕事とエネルギーの関係式を立てる問題がよく見られます。
熱力学では、気体の状態方程式はもちろん、気体の分子運動論や圧力、温度、体積の微小変化に関する近似式、ポワソンの関係式も高頻度で出題されています。
波動では、平面波や干渉条件、ドップラー効果が頻出で、位相速度や波の反射を三角関数の変形に絡めてよく出題されます。
最後に、原子分野では、ボーアの水素原子モデルや核反応などが頻出です。
いずれの分野においても、基本的な考え方、あるいは、物理の根本的な性質を問う問題が多く、本質的な理解が求められています。また、長文の穴埋め形式の問題が各大問につき10から15問程度出題される傾向があるため、問題文の誘導にうまくのって、初見の物理現象や実験に対応する応用力、そして複雑な数式計算や近似計算をする能力が求められます。
全体的な対策のポイント・注意点
物理現象の本質的な理解を問う問題が大半であるため、基礎を怠らずしっかり固める必要があります。特に教科書で書かれている公式は丸暗記をするのではなく、全て自力で証明できるようになっていることが目標です。
基礎力をつけたあとはバランスよく問題演習を行い、京都大学の問題形式に慣れることが必要です。例えば、長い問題文による誘導に、わざと途中で物理量の記号を入れ替えたり、特殊な基準点の設定にしたり、変数置換を扱ったりすることがあります。このような「落とし穴」に気づき、躓かないためには、過去問の演習を重ねて慣れることが一番の近道です。
また、京都大学の入試問題は形式がかなり特殊であるため、類似問題があまりないですが、その多くは典型問題をさらに深堀りした物理現象の本質を問う問題であることは変わりないので、幅広い問題演習を積むといいでしょう。
最後に、時間配分についてですが、京都大学の理科の試験時間は2科目合わせて180分であり、物理は大問3題あることから、大問一題につき、25〜30分ほどの時間配分が理想的と言えるでしょう。一年分まとめて演習するのではなく、一題ずつを30分ほどかけてじっくり考えて解いてみるのもおすすめです。
各問題の対策のポイント・注意点
よく出題される力学分野では、エネルギー保存則と運動方程式を組み合わせた問題や、エネルギーや運動の基準点と観測点を問題の途中で変更する問題をよく見かけます。そのため、常に状況を整理し、どの条件が不変で、どの条件が変わったのかを把握しておくことが大変重要になります。
また、電磁気分野では、一見して教科書に載っている公式と微妙に異なる数値や文字式が答えになりがちです。これは出題側が座標系を切り替えていたり、運動中に符号や観測点を変えていたりしているからです。公式をただ当てはめるのでなく、問題の状況に併せてなぜその公式になるのか、常に考えながら問題に向き合うことが欠かせません。
波動と熱力学に関しては、最初に基礎知識の穴埋めがあることが多く、それらの問題は絶対に得点したいです。年度によっては複数の連立方程式の計算や近似計算、力学や電磁気学と融合した比較的複雑な問題が後半に出題されることもあります。誘導にうまくのって、正確に状況を整理しながら丁寧に解き進めていくことをお勧めします。
化学の傾向と対策

問題構成
例年、京都大学の化学は4つの大問からなり、大問1と2は理論化学と無機化学の融合問題、大問3は有機化学、大問4は高分子化学についての問題が出題されています。4つの大問いずれも長い文章を含み、数値や語句の穴埋め問題や記述問題、そしてグラフなどの作図問題が出題されています。
各問題の出題形式・頻出分野・難易度
理論化学では、化学平衡と化学反応形式をはじめとして、電池・電気分解や分子の立体構造、気体・溶液などが頻出です。これらの問題の中に無機化学の知識が融合されていることも多いです。前半は基本公式を適用させて計算させる問題、そして、後半は実験データに関する解釈や条件変更時の考察について問う問題が多いです。数値代入の問題も見かけますが、記号計算も他大学より多く見られ、また、単純な知識問題よりも、実験設定やグラフから法則を見抜く問題が多いことも京大らしい特徴です。
有機分野に関しては、構造決定や官能基変換、反応機構がよく出題されています。また、化学平衡や速度論、架空化合物をよく扱っていることも特徴的で、基本原理で推論する能力が求められています。年度によって難易度のばらつきはありますが、多くの受験生はこの大問3で高得点を狙っていると思われます。
最後に、高分子分野では、糖とタンパク質の2つの分野がかなり高頻度で出題されています。糖類は多糖類の構造や加水分解、タンパク質はアミノ酸配列決定やペプチド結合に関する計算問題がよく出題されています。
全体的な対策のポイント・注意点
京都大学の化学は知識よりも既知の条件や基本知識から法則を推測する思考力に重きを置いています。そのため、教科書の表面的な理解ではなく、物質の根本的な性質や反応をしっかり理解するようにしましょう。
また、物理と同じように、計算問題は答えのみを書かせる問題が多いため、正確に答えを出せるように解き方だけでなく、計算力もつけていく必要があります。
各問題の対策のポイント・注意点
理論化学分野では主に記号計算、問題の誘導にのり条件変化にその都度対応すること、そして、グラフや表の読み取りとそこから立式することを沢山練習することが必要です。そのためには、まず市販の問題集を使って基本的な化学物質の性質や反応、実験操作にかかわる計算問題に取り組み、答えを導き出す過程を重視しながら知識の本質的な理解を目指すといいでしょう。
また、有機高分子化学は構造決定が頻出で必ず点を稼ぎたい分野であるため、とにかく様々な大学で過去問演習を重ねるのがお勧めです。特に、東北大学の問題は傾向が京都大学に近く、難しいため解いておくことが理想的です。
オンライン家庭教師で
京都大学に合格!
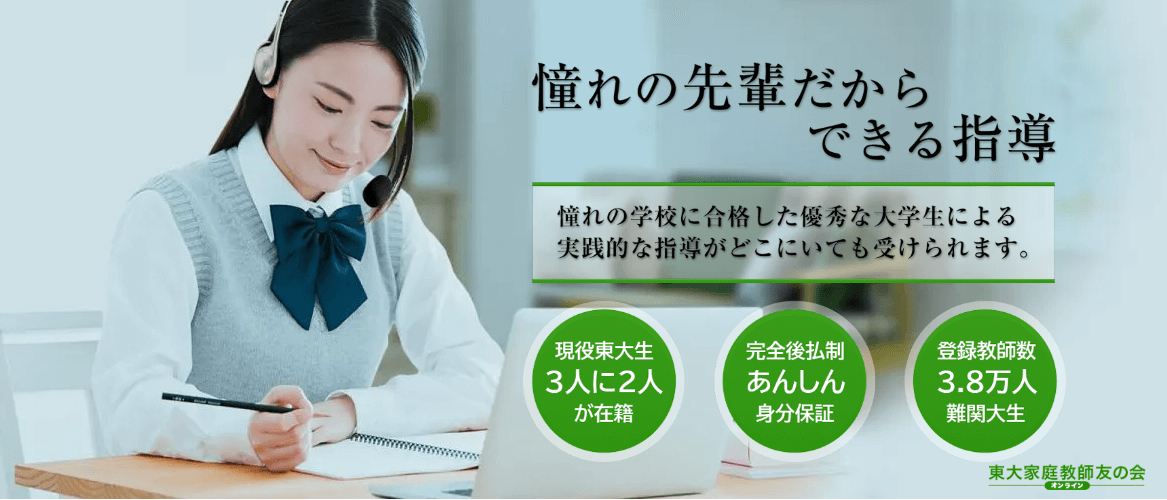
オンライン東大家庭教師友の会は、3.8万人の難関大生家庭教師が在籍する、オンライン家庭教師サービスです。
オンライン指導のため、北海道〜沖縄まで全国どこからでも難関大生による質の高い指導を受けることができます。
無料の資料請求や無料の体験授業を実施しておりますので、ぜひお試しください。
京都大学の学部/学科別の前期日程入試科目・配点
以下、入試科目・配点等の情報は全て「令和7(2025)年度入学者選抜要項」より抜粋しています。最新の入試情報は、京都大学HP等でご確認ください。
大学入学共通テストの配点に関する注釈:
国語、数学、理科、外国語など、配点が記載されていない科目は、二次試験の受験資格を判断するための第1段階選抜では利用されますが、最終的な合否を決める総合点の計算には含まれません。
総合人間学部(文系)
共通テスト・配点合計175点
国語(国語)・・・*
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から2科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・*
理科(物基・化基・生基・地基から2科目、または物理・化学・生物・地学から2科目)・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・*
情報(情報Ⅰ)・・・25点
※地歴・公民について、「倫理」と「政経」の組み合わせで2科目を選択することはできません。
個別学力検査・配点合計650点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
地歴(地理・日本史・世界史)から1科目・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B・数C)・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
総合人間学部(理系)
共通テスト・配点合計125点
国語(国語)・・・*
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・100点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・*
理科(物理・化学・生物・地学から1科目)・・・*
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・*
情報(情報Ⅰ)・・・25点
個別学力検査・配点合計700点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・200点
理科(物理・化学・生物・地学)から2科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・150点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」、「平面上の曲線と複素数平面」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
文学部
共通テスト・配点合計250点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から2科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物基・化基・生基・地基から2科目、または物理・化学・生物・地学から2科目)・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・15点
※地歴・公民について、「倫理」と「政経」の組み合わせで2科目を選択することはできません。
※上記の合計265点満点を250点満点に換算して利用します。
個別学力検査・配点合計500点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
地歴(地理・日本史・世界史)から1科目・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B・数C)・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・150点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
教育学部(文系)
共通テスト・配点合計265点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から2科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物基・化基・生基・地基から2科目、または物理・化学・生物・地学から2科目)・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・15点
※地歴・公民について、「倫理」と「政経」の組み合わせで2科目を選択することはできません。
個別学力検査・配点合計650点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・200点
地歴(地理・日本史・世界史)から1科目・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B・数C)・・・150点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
教育学部(理系)
共通テスト・配点合計265点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物理・化学・生物・地学)から1科目・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・15点
個別学力検査・配点合計650点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B・数C)・・・200点
理科(物理・化学・生物・地学)から1科目・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
法学部
共通テスト・配点合計285点
国語(国語)・・・200点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から2科目・・・200点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・200点
理科(物基・化基・生基・地基から2科目、または物理・化学・生物・地学から2科目)・・・100点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・200点
情報(情報Ⅰ)・・・50点
※地歴・公民について、「倫理」と「政経」の組み合わせで2科目を選択することはできません。また、「日本史」と「世界史」のうち少なくとも1科目を含んで選択してください。
※上記の合計950点満点を285点満点に換算して利用します。
個別学力検査・配点合計600点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
地歴(地理・日本史・世界史)から1科目・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B・数C)・・・150点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
経済学部(文系)
共通テスト・配点合計300点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から2科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物基・化基・生基・地基から2科目、または物理・化学・生物・地学から2科目)・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・50点
※地歴・公民について、「倫理」と「政経」の組み合わせで2科目を選択することはできません。
個別学力検査・配点合計550点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
地歴(地理・日本史・世界史)から1科目・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B・数C)・・・150点
外国語(英語)・・・150点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
経済学部(理系)
共通テスト・配点合計300点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物理、化学、生物、地学)から1科目・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・50点
個別学力検査・配点合計650点
国語(国語総合、現代文B、古典B)・・・150点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・300点
外国語(英語)・・・200点
理学部
共通テスト・配点合計250点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・25点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物理、化学、生物、地学)から2科目・・・50点
外国語(英語)・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・25点
個別学力検査・配点合計975点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・300点
理科(物理、化学、生物、地学)から2科目・・・300点
外国語(英語)・・・225点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」、「平面上の曲線と複素数平面」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
医学部医学科
共通テスト・配点合計275点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物理、化学、生物)から2科目・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・25点
※地歴・公民について、2科目を受験したときは第1解答科目の成績を用います。
個別学力検査・配点合計1000点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・250点
理科(物理、化学、生物)から2科目・・・300点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・300点
面接
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」、「平面上の曲線と複素数平面」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
※面接の評価によっては、学科試験の成績にかかわらず不合格となることがあります。
医学部人間健康科学科
共通テスト・配点合計275点
国語(国語)・・・50点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物理、化学、生物)から2科目・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・25点
個別学力検査・配点合計750点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・150点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・200点
理科(物理、化学、生物)から2科目・・・200点
外国語(英語)・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」、「平面上の曲線と複素数平面」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
薬学部
共通テスト・配点合計220点
国語(国語)・・・40点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・40点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・40点
理科(物理、化学、生物)から2科目・・・40点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・40点
情報(情報Ⅰ)・・・20点
※地歴・公民について、2科目を受験したときは第1解答科目の成績を用います。
個別学力検査・配点合計700点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・200点
理科(物理、化学、生物)から2科目・・・200点
外国語(英語)・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」、「平面上の曲線と複素数平面」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
工学部
共通テスト・配点合計225点
国語(国語)・・・25点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・50点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・25点
理科(物理と、化学・生物)から1科目・・・25点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・50点
個別学力検査・配点合計800点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・250点
理科(物理、化学)・・・250点
外国語(英語)・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」、「平面上の曲線と複素数平面」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
農学部
共通テスト・配点合計350点
国語(国語)・・・70点
地歴・公民(世界史・日本史・地理・倫理・政経)から1科目・・・100点
数学(数Ⅰ・数Aと数Ⅱ・数B・数C)・・・50点
理科(物理・化学・生物・地学)から2科目・・・50点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)から1科目・・・50点
情報(情報Ⅰ)・・・30点
(食料・環境経済学科)個別学力検査・配点合計700点
国語(現代の国語、言語文化、論理国語、文学国語、古典探究)・・・100点
数学(数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B・数C)・・・200点
理科(物理・化学・生物・地学)から2科目・・・200点
外国語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語)から1科目・・・200点
※数学について、「数学B」は「数列」から、「数学C」は「ベクトル」、「平面上の曲線と複素数平面」から出題します。
※外国語(英語)は「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」「論理・表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を出題。
オンライン東大家庭教師友の会が選ばれる3つの理由
ハイレベルな教師陣!
当会に在籍する家庭教師は全て難関大生または難関大卒であり、彼らは受験事情に精通し独自の勉強法やノウハウを持っています。また、採用率20%の厳しい選考を行い、教師としての指導力・優れた人間性・指導の戦略性を持った人材のみを採用しています。オンライン東大家庭教師友の会の教師の質は国内トップクラスです。
相性のいい教師が見つかる!
当会には38,000名の現役難関大生やプロの講師が在籍しています。教師数が多いということはそれだけ多くの教師を選べるということです。学習状況や希望する教師条件のヒアリングと、厳格で緻密な選考を通して、お子様にぴったりな教師をご紹介します。生徒の「勉強をしたい」という気持ちを育てることができる教師陣です。
安心して利用できる!
指導状況を把握できる指導報告書や教師交代など様々なサポート体制を整えております。オンライン家庭教師が初めての方でも安心してご利用いただけます。また、料金は完全後払い制で毎月指導を行った分だけ指導料をお支払いいただきます。教師交代費、授業キャンセル料、解約費、更新費、再入会費、兄弟/姉妹入会費はすべて0円です。
学習コーチコースのご案内
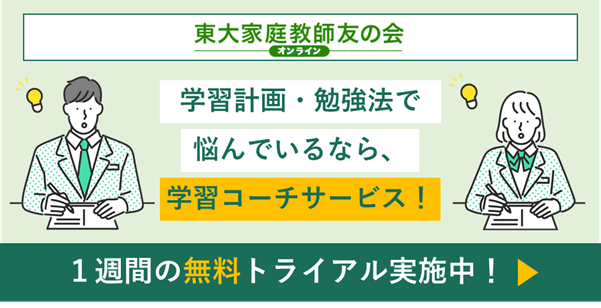
「そろそろ受験勉強始めなきゃとは思ってるけど、進め方が全然わからない…。」
「この勉強法で本当に合格できるかすごく不安…。」
「一人じゃだらけちゃって、勉強が進まない。」
そんなお悩みに、学習コーチが答えます!
実際に難関大学に合格した先輩が、あなたの学習計画・勉強法にアドバイス!
毎日チャットで勉強の管理も行います!
1週間の無料体験指導も実施しておりますので、ぜひお試しください。
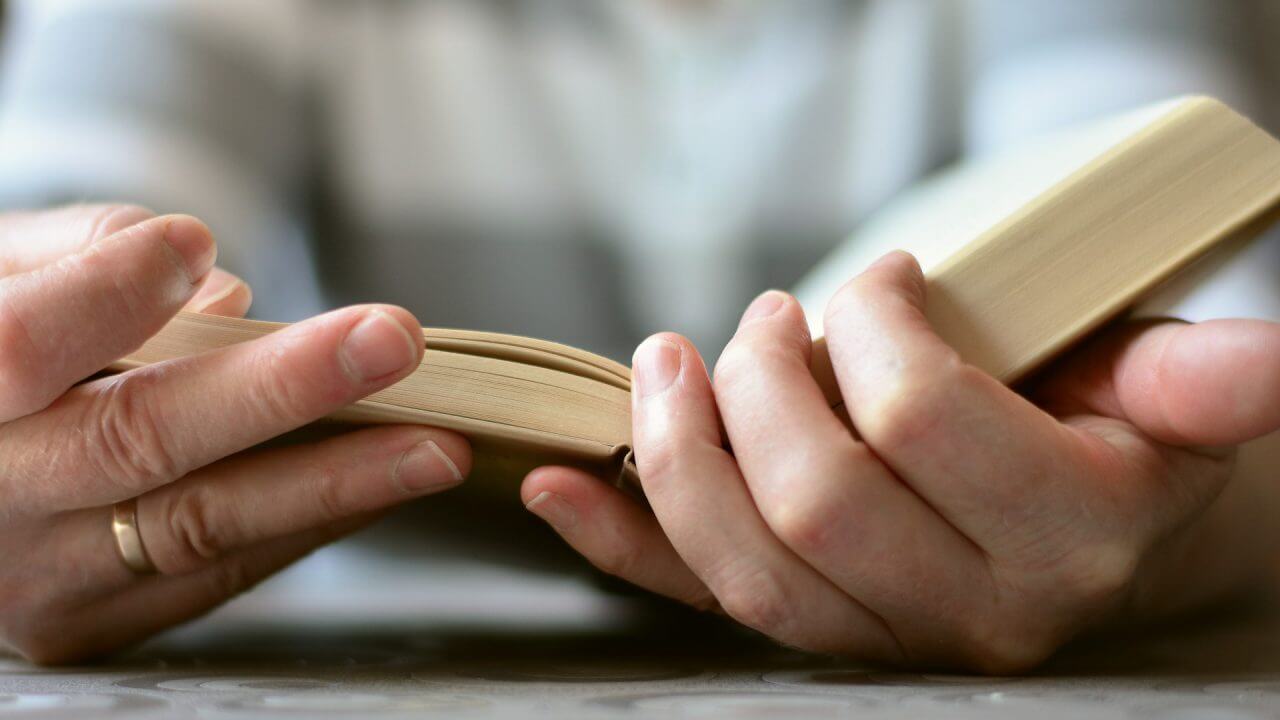
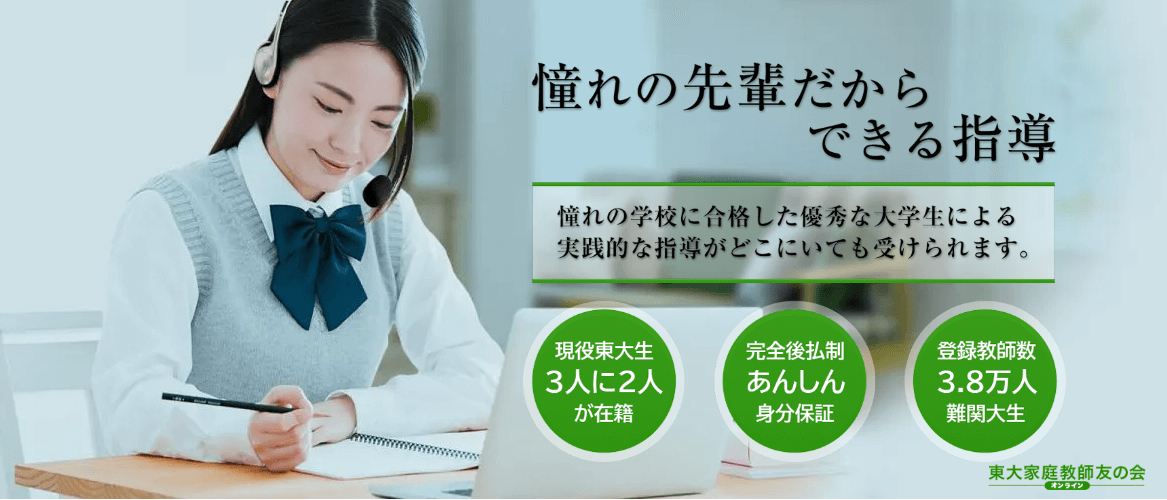
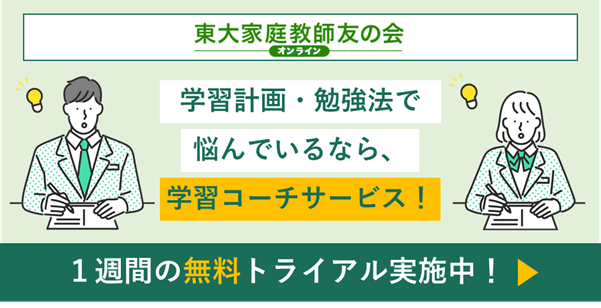
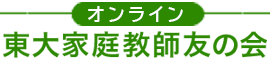





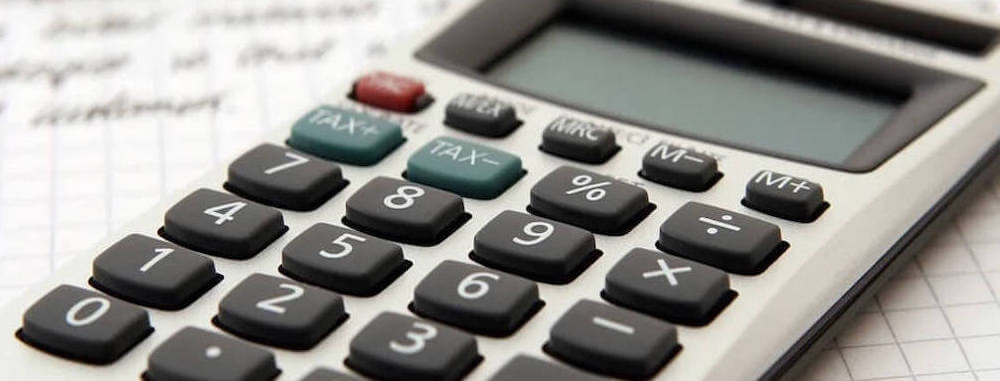

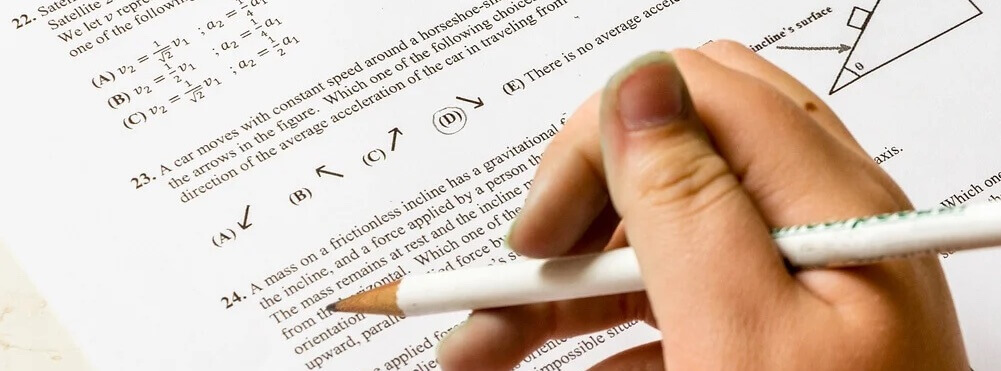

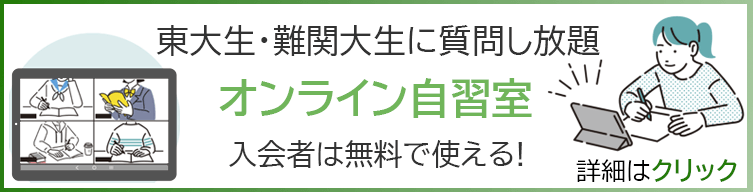
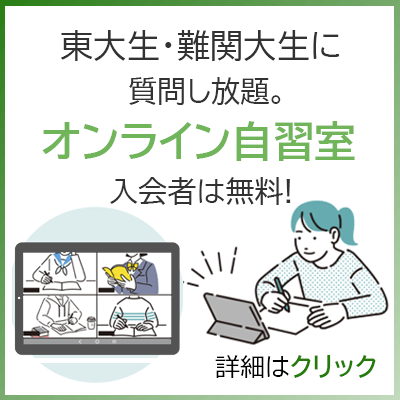
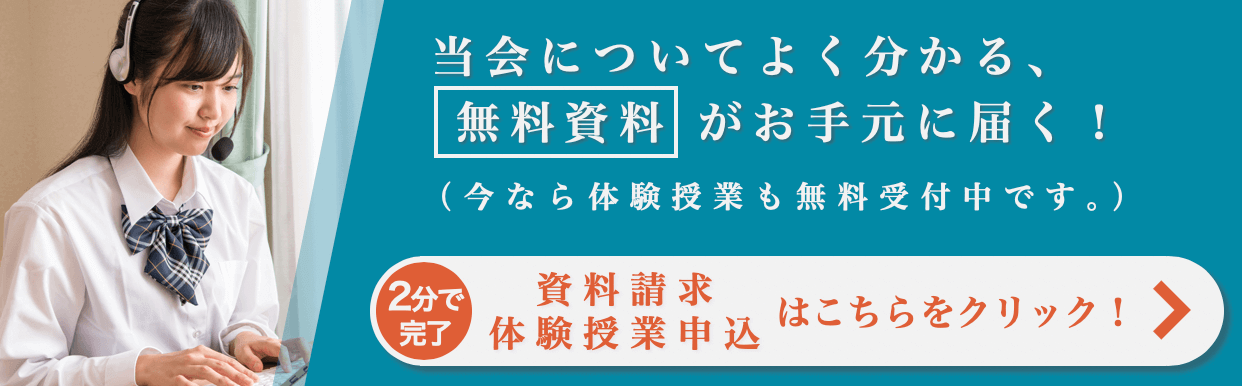
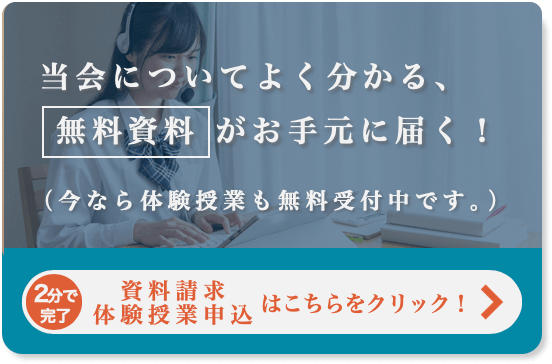
先生や友人など、様々な人と問題についてたくさん話しましょう。苦手教科ほど頼れる人を作っておくのは重要です。できる人の視点や方法を積極的に取り入れると、苦手教科でも解く力が育っていきます。
また、受験勉強においては、計画を立てることもとても大切です。日々のタスク管理から、何の教科で何点取って合格するのかという得点計画まで、自分なりに見通しをもって勉強をすると、日々がただつらいだけではなくなります。京都大学はハードルが高いように思えますが、戦略を立て、解答の精度を高めていけば合格することができる大学です。どんなに状況が悪くとも、諦めずに自分が合格する方法を探し、自分が持っているものを最大限活用して下さい。
驕らず、卑屈にならず、一歩一歩進んでいく。それだけが、合格にたどり着くのに大切なことです。応援しています。